
組織行動とリーダーシップ
環境が変化し続ける中でリーダーとして影響力を発揮し、組織を動かすにはどのような行動を取るべきか。 どのようなリーダーシップスタイルがあるのか。 また、組織・メンバーを導くためのエンパワメントの手法にはどのようなものがあるのか。 多くのビジネスパーソンに深く関係する、組織行動とリーダーシップについて、 理論と事例を交えながら理解を深めていきます。 組織行動とリーダーシップを初めて学ぶ方は、以下の関連コースを事前に視聴することをお薦めします。 ※グロービス経営大学院およびグロービス・マネジメント・スクールにおける受講科目の教材として本動画を視聴される場合、関連動画はご視聴いただけない場合がございます。 ・リーダーシップとマネジメントの違い ・エンパワメント ・X理論・Y理論 ・PM理論 ・動機付け・衛生要因
会員限定

















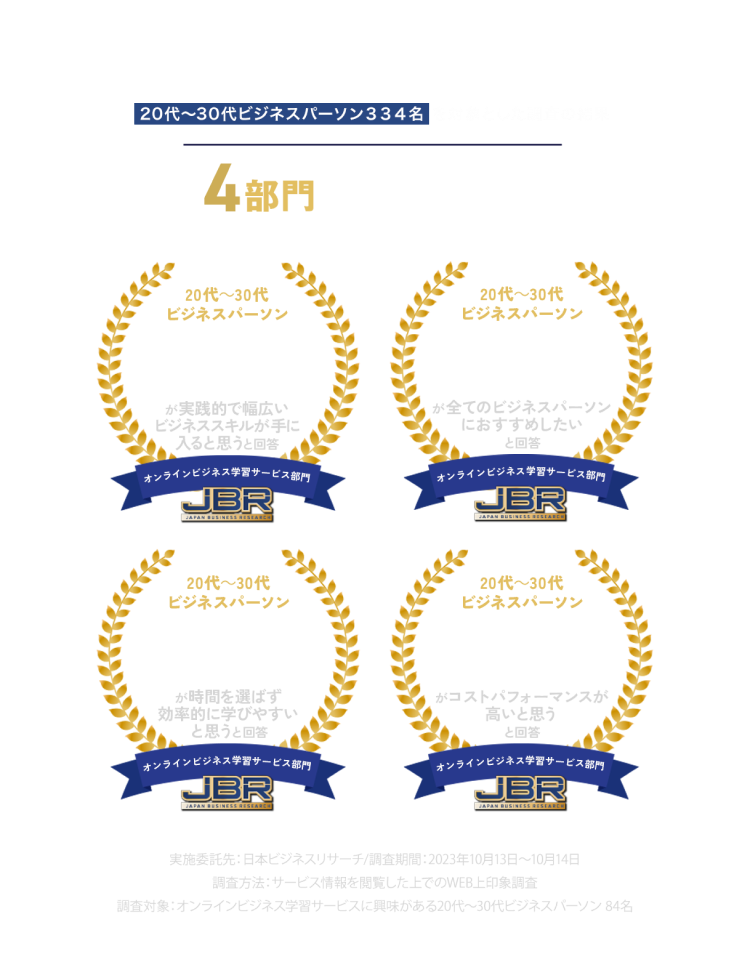

より理解を深め、他のユーザーとつながりましょう。
100+人の振り返り
ojr_800
メーカー技術・研究・開発
マネージャも業務を抱え過ぎて部下への細かいケアが行き渡らない現実もあり組織単位としては少人数のブロックを多く作った方が良いのではと思います。あとは階層構造は出来るだけフラットな方が自分としては良いかなとも思います。
gs51
その他
パフォーマンスが低い人に対して、ただ苦言を伝えるのではなく、「2-6-2の法則」や「適性」を踏まえ、観察・対話による状況把握、適切なアドバイス・支援や適材適所に基づく役割見直しなど、パフォーマンス底上げにつなげたいと思う。
koichi_0502
その他
2-6-2の法則、全ての人を積極的に働くようにするのは難しい事が分かった。パフォーマンスが低い人にも役割がある。みんなを同じ水準にするのは難しく感じていたが、それぞれの役割の中でパフォーマンスを上げやすくするサポートをする事なら実践出来ると感じた。
sasami-mi
専門職
組織が成長する上で、全員に高い期待をしてしまいがちだが、人それぞれに成長速度があり、その結果
このような法則が生まれる原因もあると思うので、その人にあった得意を見つけつつ、成長速度にあったフォローをすることで、生産性の向上や、離職率の低下にもつながると思った。
この考え方を生かし、できない理由を探すよりも、この人の得意なことを見つけることにフォーカスしていきたい。
masakazu_takase
その他
業務において成果の出ていない人の教育に悩んでいました。大切なことは、一人ずつ面談して課題や要望をヒアリングしてその人が納得してモチベーションの上がる育成や指導が必要だと感じました。できる人を真似ろでは成果が出ない理由が少しわかりました。
tsubamoto_
営業
2-6-2の法則はよく聞く法則であり。どの様な組織でも起こりうる事である
全体の平均値を上げる事で下位20%の組員は社外から見れば下位ではなくなる
halkuma
専門職
PLの仕事の回し方にfb可能
youhei-okabe
経理・財務
下位メンバーの扱い方に留意する
jetshero
その他
適材適所の配置について具体的にわかりやすく学ぶことができた。
yuji-fukuniwa
人事・労務・法務
ヒアリングが最も有効な対策だということを理解出来ました。
peperoncino
営業
高いパフォーマンスを発揮する上位20%はその意欲を十分に維持し、中位60%でもその中での上位20%のパフォーマンスを上げていく。また下位20%とのコミュニケーションを十分に取り、支障をきたす障害などを取り除く配慮も続けていくことが大事となる。
kouw
販売・サービス・事務
この法則を念頭において適材適所を検討して成長視野にした対話を行なっていく
saikikoichi
経営・経営企画
パフォーマンスの低い人に
統括部横断共通業務を与え
トライアル開始したので結果が楽しみである
y-arano
メーカー技術・研究・開発
2-6-2の法則は知ってはいたが、対処法までは考えたことがなかったので、今回の学習は有効であった。
同じ部署内でなんとか輝ける方法を見つけることも大事だが、他の場所で輝ける場所があるのであれば思い切って配置換えすることも大事であることを念頭において部員の指導をしていきたい。
andy2024
メーカー技術・研究・開発
組織の中にいる全員が自分のポジションを知るべきなのかが悩ましい。特に上の人に対して「あなたは上の2割の人なのだから、下の2割の人たちにイライラしたり、圧をかけたりしないこと」ということを明確に言ってあげた方が良いのかどうか。
nicoe
資材・購買・物流
下位2割に対し、ヒアリングすることを心がけ致します。
seiichiro_3135
経営・経営企画
2:6:2の法則とは、パレートの法則から派生した法則で、どのような組織・集団であっても「優秀な人:普通の人:できない人(むしろ足を引っ張る人)」の割合が20%:60%:20%になるという法則です。262の法則は、かなり多くのことに適用できると考えられており、先ほどの優秀・普通・できないの2:6:2だけでなく、どのような集団であっても構成要素の上位:中位:下位をの比率が2:6:2になるという法則とも解釈されています。例えば、
社会では、高額所得者が2割:庶民が6割:貧困層が2割
自分に対して、好意的な人2割:なんとも思ってない人6割:嫌いだと思っている人2割
アリの群れでは、働き者のアリが2割:普通に働くアリが6割:怠け者アリが2割
など、集団に対して、色々な面で内訳が2:6:2になると考えられます。また、例に挙げたアリのように人間以外の集団についても同様の比率が成立すると言われています。そこから転じて別名、働きアリの法則とも呼ばれています。
この2:6:2の法則をもとに、どうしたら上位2割の優秀な人材を増やし、強い組織を作ることができるかを考えてみます。
anyo
金融・不動産 関連職
組織運営する中で誰それさんが仕事しない、と言う愚痴は常に存在する。言っている側の意見も尊重しつつチーム力で目標達成していく事の大切を伝えようと思う。
ken175
メーカー技術・研究・開発
得意な分野の仕事を回すようにし、またそのアウトプットに感謝を示して、モチベーションをあげるようにする。
kawakami
金融・不動産 関連職
適材適所は実現できると素晴らしいですが、組織全てで実現するのは簡単じゃないこともあると思います
wakameudon
メーカー技術・研究・開発
他のメンバーがハイパフォーマンスを出せないことに対してイラつかない
ryu0358
メーカー技術・研究・開発
実務で役に立つ考え方を理解できました。
y_su
人事・労務・法務
全員を働き者にすることはできないと知れたことが大きな成果でした。
morima-m2
メーカー技術・研究・開発
262の法則があることを念頭に置きつつも、みんなに興味関心を持って接する!
ksoufuku
メーカー技術・研究・開発
2-6-2の法則は聞いた事はあったが、適正を踏まえた配置転換などは初めて学びました。実践してみたいです。
h-ku
コンサルタント
下位を排除するのでなく、適材適所でポテンシャルが発揮できるようマネジメントを心掛けたい。
8902686
専門職
2-6-2の構図を正しく理解したうえで、職場のマネージメントに活かしていけば、バラスの良い組織になると認識した。
koji_wada
マーケティング
2-6-2の法則
優秀20%、平凡60%、怠け者20%
働き蟻の法則とも言う。あらゆる集団において上記のようなバランスになってしまう経験則。全員を優秀にするのは無理だが、できるだけ多くの人がパフォーマンスを発揮できるように環境や役割を整えて、マネージメントをすることが重要。最適配置、適材適所が肝要である。
k_anazawa
建設・土木 関連職
自組織に対して考えると
けして262では無いと思います。
ki12
販売・サービス・事務
今自分が直面している課題の一つである。
チームメンバーのスキルはそれなりに高いものが
あると感じるが、モチベーションや仕事に対する
ウィルを感じ難い。
しかし、自分のヒアリングが不足している
のが原因の一つかもしれないので、まずは
チームメンバーと話し合いながらより良いチーム
を作っていきたい。
shirai-t0804
金融・不動産 関連職
2-6-2の法則、確かにどの組織にも存在しているように感じます。だからといって、パフォーマンスが低いメンバーをあきらめるのではなく、適性を見極めて適材適所への配置を検討することが大事だと思いました。
ftec
メーカー技術・研究・開発
適材適所で対応したいが、厳しい職場や緩い職場が存在するのが事実である。
前者の下位20%を後者の職場に異動することや既存の職場で業務不可を下げることはなかなか難しい。
適正云々出なく、仕事への姿勢やモチベーションも重要だと思うので人事施策などで仕事の姿勢などを全社員に浸透させたい。
人事考課での処遇のメリハリやストレングスファインダーでの適性診断などできる施策をやっていきたい。
ko-ki-
人事・労務・法務
人事部の立場で活用する場合、他部署の上位20%をしっかりと把握して新卒のメンターや研修講師に充てて新卒の成長を促す。
shira-jun
IT・WEB・エンジニア
働きアリの雑学は学び
kurocoro
人事・労務・法務
メンバー個々に1on1ミーティングを行い、個人の強み、弱みを把握し、業務のアサインメントの参考とし、メンバのやりたいこと、目標に少しでも近づけていけるよう寄り添いながら、個々のモチベーションを下げないようにマネジメントを行う。
個々が働きがいを持って目標に近づくことが出来れば、おのずとパフォーマンスは向上し、活気があるチーム運営へ変化させることができる。
masahirok1225
経理・財務
そもそも優秀の定義を明確にする必要があると思いました。優秀とは人によって定義がバラバラです。その統一が必要と判断します。
hontake1202
人事・労務・法務
残念ながらパフォーマンスの低い人は存在する。その人にヒアリングをし、適材適所を考えパフォーマンスを向上させることを考えることで組織全体のパフォーマンス向上につなげることができる。
190586
販売・サービス・事務
自分自身がパフォーマンスの低い20%になりたくないと強く思います。受電をするTCさんが平均以上のパフォーマンスを出せるようにフォローをした意向と思います。
shimizu_shuichi
メーカー技術・研究・開発
パフォーマンスを発揮できていない下位20%に該当すると思われるメンバーに対しては、アウトプットを求めるのではなく、強みを理解した上でチーム編成等マネジメント側での対応が必要なコトを理解した。
piro_15
営業
全員を働き者にできないことを理解する。現組織を振り返ると下位20%の人にも他の80%の人同様のストレッチがかかっている現状で、下位20%の人にとってはこれがストレスとなっているのかも。ストレスからの他メンバーとの歪みが生まれ、結果的に組織の雰囲気も悪くなる場面が多い。各人の強み弱みキャリアプランを理解し、業務をアサインすることで働きやすい環境づくりに努めたい。
yasu-_-123
メーカー技術・研究・開発
パフォーマンスが低いメンバーが20%いることは、しょうがないと言うことを念頭に、業務分担と配置を考える必要があると、理解した。
sphsph
メーカー技術・研究・開発
致し方なし。
それを理解しつつ最大のパフォーマンスを出す。
miyazaki_yosuke
メーカー技術・研究・開発
参考になりました。適材適所ということですね。
yuya-sekido
専門職
どのような集団でも2-6-2の法則が当てはまる為、全員を上位20%のレベルへ引き上げるマネジメントを行うのではなく、下位20%は適材箇所や適材業務を模索し与えることが組織として重要だと思った。
haro555
その他
自部署でも2-6-2の法則が発動しています。すべて改善することは不可能であると認識する、という点は、あきらめということではなく、かえって前向きに問題をとらえることができると思いました。パフォーマンスが低いコミュニケーターには、現状認識の面談を実施しできるところを引き出し、良いところを伸ばすよう働きかけていきたい。
hiroaki5163
営業
メンバーを2-6-2で分類して考える。
ab0110
専門職
全員がパフォーマンス高い集団は存在しないのがなんとなくわかった。
otsukin
営業
何もマネジメント業務をしなかった東京の上司を反面教師にして、自分自身が管理職になった際は、同じ被害者を出さぬ様、今回の様な学習にも精を出す。
ryukei
営業
人数が少ない部署内でも2-6-2の法則が起きている。できる人にばかり仕事が集まり不満が出て、6-2の人は課題感を持って仕事ができていない。仕事を均等に与えることも大切だが少ない人数だからこそ大胆な役割分担を行うことも視野に入れるべき。
iwatanobuaki
建設・土木 関連職
組織には必ずパフォーマンスの高い人低い人がいることを理解して、マネジメントする際には別の部署の方が適性があるかも含めて考えてあげる必要がある。
yoshihide-s
その他
実際の現場ではなかなか新しい適切な仕事は難しい気がする。
kazuya5225
その他
今回の2-6-2の法則は組織で確かにっと思う法則だと思いました。出来ない人を出来る様にするのではなく、全体のバランスを見て、適材適所で使う方がチームの為と納得致しました。
takahira15005
専門職
理解できた!
良かった!
suikinchikamo9
その他
この経験則があることを言い訳にして、全員ハイパフォーマンスカルチャーをあきらめることはしないようしないといけない
muneyukif
メーカー技術・研究・開発
パフォーマンスの低い人がいるのは組織として当たり前で、かつ、その人がポジションを変えれば能力を発揮する可能性を忘れないことが重要だとわかった。
dus221
人事・労務・法務
過去に運営していた支店でパフォーマンスの低い20%のグループに対し、個人ベースのアプローチはしていたものの、具体的にパフォーマンスを上げられるような環境に移動させることは組織が小さいためできなかったことが理解できた。ベターな環境に改善することはできたのではないかと反省している。新年以降は具体的なアクションプランを作り、実現していきたい。
eizan_1000
IT・WEB・エンジニア
隠れた能力や役割、存在感を見つけてみようと思う。
clover_09
販売・サービス・事務
2-6-2の法則を初めて聞きましたが、実際に自分の部署や隣の部署が法則通りで驚きました。
パフォーマンスが低い人が腐らず業務ができるようにヒアリングを行うことが大事だと感じました。
yuya-shirai
メディカル 関連職
やはり本人との面談はヒアリングを定期的に行うことでパフォーマンスがうまく発揮できていないときでも素早くキャッチすることができます。
youyoutaka
販売・サービス・事務
2-6-2の下位20%の方への対象方法を学べた。何が弊害で生産性が悪いのかヒアリング等で確認すると思に、その人に合った環境や業務を与えることが重要
pontaro-
経営・経営企画
働きかけを行ってもパフォーマンスが上がらない社員をどうするのかが難問。
osamu-16
その他
各人の個性、能力を理解して、適材適所へ配置する。不得意作業についても指導や教育の場を提供する。
takuya_hidaka
経営・経営企画
私は262に法則で評価され、下位2と評価された結果、よりよい会社への転職が決まった。
ben3369
その他
現在の所属部門で若手・新人の教育担当をしている。職場内の諸活動(安全・5S・改善提案など)のリーダーを割り振って、職場内での活躍を促しているが、各自の意欲・パフォーマンスに差が出始めている。低パフォーマー者にはヒヤリングをおこない、本人の特性(好きなこと、特異なことなど)を聞き出し、リーダーシップの習熟法に反映させようと考えている。
tsumai-masa
専門職
パフォーマンスがあがらない人に対して、厳しく当たるのではなく、どの集団にも一定数の割合で存在することを意識して、最適な業務をアサインするように心がける
kurokaz
メーカー技術・研究・開発
パフォーマンスの低い人の適性を判断する
mi-yu-king
販売・サービス・事務
この法則を知ることで、原理を学ぶことができた。パフォーマンスが低い人にはヒアリングすることで少しでも意識が変わればよいと思いました。適材適所に置いてもまた新たな262が始まるなら、ヒアリングを続けることや雰囲気を変えられるようすることも大切だとも思いました。
eisukes
販売・サービス・事務
適性を判断して適材適所の配置を行う。
yu0610015
営業
リソースの最適化が組織全体のパフォーマンスの質、量を上げることに繋がると感じた。
massapy
経営・経営企画
2-6-2の法則で重要な示唆は、下位20%の存在を理解し、適切なアプローチで働きかけや再活躍の場の提供をする事にあると思います。
逆に、下位20%を上位20%にすることに注力する事は、生産的とは言えないと思います。
組織マネジメントにおいて、生産的とは、この経験則をもとに、下位20%の存在を認め、そして新たな活躍を模索する事だと感じました。
ye02196
その他
集団の中にはパフォーマンスの低い20%が存在することを認識して、その人たちにいかにパフォーマンスを発揮してもらうかがマネジメントの役割だと思って行動する。
ko_to
営業
全体の割合からは2:6:2になる傾向があるとしても、低いパフォーマンスとされる2の底上げをするにはどうしたらいいのかを考えることが大切に感じた。
m-masa-2311
その他
下位の人材の接し方が理解できた。上位、中位の人材の意識を維持させる方法も学びたかった
yusuke0358
販売・サービス・事務
個性は唯一無二で有るように多様性を認め、パフォーマンス最大化に向けコミユニケーションを密にしていく。押し付けではなくフランクに声掛けし合える関係から先ずは進める。
915684w
マーケティング
2-6-2の法則の内容が分かり易く解説した有った。
どの集団にも一定数動けない人は居る。
スキルやパフォーマンスの低い人を開花させるには、コミュニケーションが大切だと感じた。
その人の適材低所は必ずあると感じた。
akinobu-t
建設・土木 関連職
1on1などを活用し、各メンバーの業務進捗だけでなく、強みや得意分野や希望の職種を確認すると共に、不足している能力の補い方について共に考えたいと思います。
masa-toku
資材・購買・物流
全ての人に公平公正とは行かないが誠実さと対等である姿勢がリーダーには必要だと感じた。2−6−2の考え方はアンガーマネジメントの思考のコントロールで生かそうともう。
imahori1203
営業
下位20%をやり玉に挙げる組織が多い中で、そのメンバーの可能性を引き出す方法を考える方が生産性が高いことが良く理解できた。
haruka_san
販売・サービス・事務
パフォーマンスが低いメンバーが存在することを理解することが必要だと思いました。パフォーマンスが低い方々へは、叱責や放置ではなく①~④を行っていきます。
①何に対してパフォーマンスが低いのか観察 ②モチベーション管理 ③進捗状況の把握と定期報告 ④具体的なフォロー内容提示と行動改善の促し
alpina_b3s
販売・サービス・事務
2-6-2の法則は、以前から認識していましたが
改めて学習することでより理解が深まりました。
kayo_sek
その他
集団において、全員がやる気をもつことは難しいと理解する。その上で仕事が出来ずモチベーションが低い人でも、適材適所でモチベーションが上がり、戦力となりうることを理解して、その人に合う仕事、ポジションを見つけるようにする
axtyu
IT・WEB・エンジニア
あらゆる組織には2-6-2の法則が働くことを理解し、パフォーマンスの低い人をむやみに批判するのではなく、業務によってはパフォーマンスがあがることを理解して、相手にヒヤリングする
kari_13
メーカー技術・研究・開発
この経験則を知っていれば、メンバーのパフォーマンスをマネージングするのに有用である想像ができた。
shinano777
人事・労務・法務
2-6-2がいることを理解し、一律ではなくレベル感にあわせて目標を立てを行ったり、業務の指示を行い、動機づけをしていきたいと思います。その中で話しやすい雰囲気作りであったり、信頼関係を高めていけたら良いと感じています。2-6-2それぞれのレベルにあわせてすすめることで、全体的なボトムアップにつながると思いました。
katsu_takahashi
専門職
部門におけるアウトプットの低いメンバーへの働きかけと適材適所配置の更なる理解
s1160718
営業
下位20%の方にその自覚があるのかからはじめたい
nyagoaki
金融・不動産 関連職
各人の得意分野や関心事に応じた仕事の割り振りが必要であることを再認識しました。
mike5024
経理・財務
やはり定期的な異動でチームを組み替えることにも、個々人の能力発揮の上で意味があるのだと理解しました。
suzuki_emi
その他
パフォーマンスが低い人に対して諦めるのではなくどうしたらその人の個性を活かしてチームに貢献している実感を得てもらうかを考える。
hide-nakagawa
その他
組織運営において
成果に結びつかない人に対して配置変更、業務変更をし
組織の成果に繋がる行動をとる為には必要な知識である
satou_saori
メーカー技術・研究・開発
人には向き、不向きがあるので、個人の特性を理解し、適した仕事を振ることで、チームの生産性向上になると感じました。
koyaokuda
営業
ありがとうございます
kabu_58
経理・財務
2-6-2の法則を知ったうえで思ったことは、上位2割にいるような人は、仕事ができるため各部署から様々な問い合わせが来てその人だけに業務が集中する、というような状況が起きているので、その負荷を分散させるような仕組み作りが今後できれば・・と感じた。
unnkokusai
クリエイティブ
国会議員にも言えるのでしょうか、もっとも日本は優秀な?財務官僚による統治国家。
さて、◎田首相はどの階層に入るのでしょうか。
ymori_
営業
2-6-2の法則は、パフォーマンスの高低はやむを得ないと考えることにつながると思うが、一方で人材育成の重要性は忘れるべきではなく、人材が組織の中長期的なパフォーマンスに影響を与えることも考えながらマネージしていきたい。
asami_nmr
営業
パフォーマンスの低い社員について、何がやりたくて何ができるか、現状の業務とのギャップをどう考えているか、きちんと話し合いしたうえで、適材適所を再度検討したり、意識付けする必要があると考えました。
soya030024
営業
社内の新入社員や若手社員を中心とした人員配置、育成計画、組織の生産性向上にもつながるマネジメントに活用できる
takuroro
メーカー技術・研究・開発
自分自身においても、最近パフォーマンスが上がらないと感じる状況になった場合には、何が原因なのか立ち止まって考えるようにしたい。そのときには、また自身の強みや特徴を再認識しつつ、足りないスキルにも着目して研修や経験を積んでいく行動に落とせるようにしたい。
mayfujiwara
販売・サービス・事務
パフォーマンスが悪い人にも事情があると考えてヒアリングが必要とのこと。
問題点が改善されればチームの雰囲気は良くなると思う。
モチベーションが低い場合は上げるのに時間と労力が必要と思うが、うまくいったら得るものは多い。
sanaki
マーケティング
まず、このような割合でメンバーが構成されてることを意識します。