
NPOと行政の連携「支援のネットワーク」の仕組みづくり~五十嵐立青×小林史明×白井智子×髙島宗一郎
G1サミット2022 第6部分科会P「ポストコロナのグランドデザイン -必要な人に速やかに支援を届けるための仕組みづくり-」 (2022年3月20日開催/沖縄万国津梁館) コロナ危機において私たちは、現場の基礎自治体やNPOの努力にもかかわらず、真に支援を必要とする人々に対して十分な支援が届かないという、現状の制度とシステムの限界を突きつけられた。コロナ危機の教訓を踏まえて我々が克服すべき課題と目指すべき道筋はいかなるものか。貧困支援に取り組んでいるNPOなどと行政が連携し、網の目のように支援のネットワークを張るための仕組みづくりとその方法論まで、具体的に議論を展開する。(肩書きは2022年3月20日登壇当時のもの) 五十嵐 立青 つくば市長 小林 史明 自由民主党 副幹事長 衆議院議員 白井 智子 NPO法人新公益連盟 代表理事 髙島 宗一郎 福岡市長
無料

















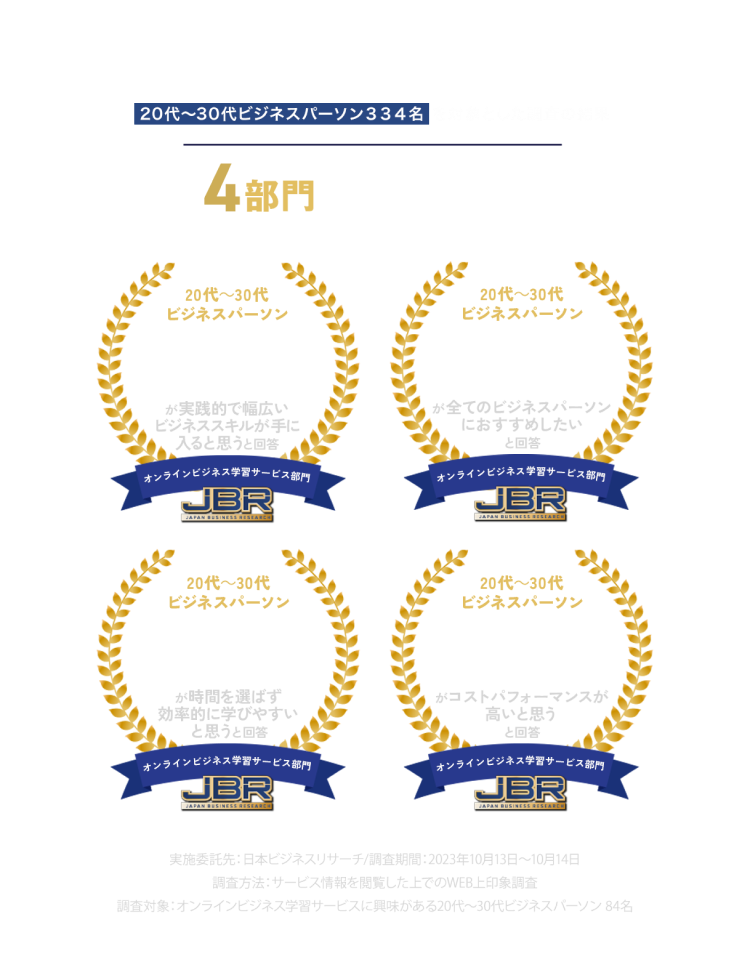

より理解を深め、他のユーザーとつながりましょう。
25人の振り返り
pukakiblue
営業
養育料を日本では払ってるのが、2割で他の国ではパスポートや免許が使えなくなるという話があったが、厳しく取り立てて欲しい。
ma2022
営業
重層化、多層化している課題に対しては縦割りでは効果的な対応が難しく、横断的な組織や機能が重要性を増していると思う。どこに問題があって、どのような改善が図れているのか?データで定量分析すること。また子どもたちと社会・家庭との適切な距離感をとること。突き放さない、過保護になりすぎない、個性の尊重や自立を支援する仕組みや工夫を実行していきたい。
kiki0410
人事・労務・法務
コロナ禍、マスク生活が当たり前の子供達は、人とのコミュニケーションが苦手になっているような気がします。まさに犠牲になっているのは子供達だと感じました。
takumi_1453
経営・経営企画
教育サービスの多様化と受け入れは文部科学省の手に余るので、文科省や経産省の組織を一部再編して教育庁を独立させるくらいの大胆なアプローチが必要と思います。
kfujimu_0630
マーケティング
コロナによって様々な課題が浮き彫りになってきました。これをピンチと捉えるか、チャンスと捉えるかで行動が変わってきます。課題解決のチャンスと捉えて行動したいと思いました。
oka7712230
営業
子供や、女性が、現在どうしても、犠牲になっている事を知りました。データがとても重要と、わかり、予防が大事という事が、印象的でした。
somosan_45
その他
教育は社会的投資が求められる重要な対象の一つだと改めて思います。行政のみならず、多くのステークホルダーからの資源を投じて、未来の社会を支える動きがもっと大きくなると良いのですが。投資と捉えるためには、どういったインパクトを生みだせるかを示すDataも必要になってくるので、Dataを扱えるよう、個人情報に対して過敏になり過ぎているところと、鈍感なところのアンバランスも是正する必要があるのでしょうか。
tanruka-55
その他
見えない貧困や困難を抱えている子どもたちを見える化するというマクロ的な取組の重要性を感じると共に、すでにミクロの働きをされている方々への尊敬を覚えました。自分も力を付けて、そこにコミットしていくために今の学びを大切にしていきます。
mayumiya_m
その他
見える化は必要だと思う。
eripond
IT・WEB・エンジニア
子供たちや女性など弱者の置かれた課題を、データによって浮き彫りにすることができる、という視点が新鮮でした。
carlos_17
クリエイティブ
細かい所ですが「問題を起こしそうな人を予防する」という言い方だと
対象になる人はとてもネガティブな印象を受けるだろうなと感じ、
翻って呼び方は大事だと感じました
makoto_97
営業
他人事ではなく、自分ごととして考えないといけないのだと思います。
sai-3448
人事・労務・法務
今回学んだことを参考にしたいと思います。
fujiyoshi1215
販売・サービス・事務
仕事に役立つ授業ですね
maru-taira
建設・土木 関連職
コロナが1つの分岐点として、今まで先送りにしてきた問題、表面化してきた現実、これから考え得る未来、それらにどう向き合うのか?
向き合う為に行動していきたい
cozyhayakawa
営業
教育を民間がサポートする仕組みや仕掛けがよりコロナを経て加速させる必要を感じます。
社会環境の変化で既に教員という一面的な指導、ティーチングでこの世の中を渡り歩く子供を育成することが限界にきており、働き方・適性労働の観点から教員もこれまでのような指導時間の確保が難しいと状況に突入したと思われる。
より変化する社会で渡るには多様な社会の事実に触れ、非認知能力を高める学びの機会を増やすのがよいと思いました。
民間とのコラボも含め実験的な指導を積み重ねて行くこととおもいますが、同時に企業にもビジネスチャンスが増すと思うのでぜひこのような動きにがドライブするような実践を行いたい。
sphsph
メーカー技術・研究・開発
弱者!?
怖い言葉です。
対して強者がいるんです。
大多数のその人たちが一歩踏み出さなければ何も起こらない。そのために小さな一歩を繰り返す。
kaori_c
金融・不動産 関連職
コロナ禍で子供たちの教育格差は深刻な問題だと思う
sakika___
販売・サービス・事務
とても勉強になりました。
takanami73
金融・不動産 関連職
息つく暇もない有意義な時間でした。
発達障害のこどもがいるので、時に涙しながらききました。
行政、NPO、企業が連携していくことの重要性を感じるとともに、自分に何ができるのか、今の仕事を続けていいのか?などいろいろ考えが巡ります。
世の中を変えていこうというアツい気持ちが大事だよなと、改めて感じました。
12121212
営業
教育格差の問題を認識できました
yumaka
販売・サービス・事務
データ化したことで子供の問題が重複している事がわかった件にもあるように、見えなかったものを見える化させる事はとても大切。
STAYHOMEのHOMEが危機的状況である子供達がいる、「親権(=親の権利)」ではなく「親の責務」に言い換えている国が増えている等、自分の価値観や常識をアップデートしていく必要性を感じた。
ビジネス面で出来る事とは、という問いに、コロナ禍等の大きな危機的直面でも企業が自立して社員やその家族・子供を守れるようにという意見も貴重だった。
kubota_kazuhiro
IT・WEB・エンジニア
コロナ禍でテレワークが進み、新たな働き方を急速に行ったので、多くの課題がありますが、一つ一つの課題に向き合って見える化させていかないといけないと感じました。
ruru_ruly
経理・財務
現状の教育現場の問題点などについて活発な議論を伺えた
hi_ma_hi
販売・サービス・事務
とても勉強になりました。