
プラットフォーム ~プラットフォーム型ビジネスの基本構造~
GAFAにとどまらず、Airbnb、Uber、アリババ、テンセントなど、「プラットフォーマー」と呼ばれる企業が著しい成長を遂げているのは皆さんご存じのとおりです。 このコースでは、テクノベート時代のビジネスを考える上で極めて重要である”プラットフォームビジネス”の基本的な考え方を理解することを目的としています。 プラットフォームビジネスが発展してきた背景や、これらのビジネスの特徴などを踏まえ、事例も交えながらわかりやすく解説していきます。 ☆関連情報 フレームワークでニュースを読み解く、日経電子版の記事もぜひご覧ください。 「ヤフー・LINEが挑む「終わりなき消耗戦」」 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO52381940Q9A121C1000000/?n_cid=DSPRM5277 「アップル対フォートナイト、独占巡り強者同士が激突」 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO63360780S0A900C2X12000/?n_cid=DSPRM5277 「韓国BTS事務所はプラットフォーマーになれるか」 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC014Z40R00C21A8000000/?n_cid=DSPRM5277 「Facebookは巨大プラットフォームから脱落するのか」 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC214UG0R20C22A2000000/?n_cid=DSPRM5277
会員限定

















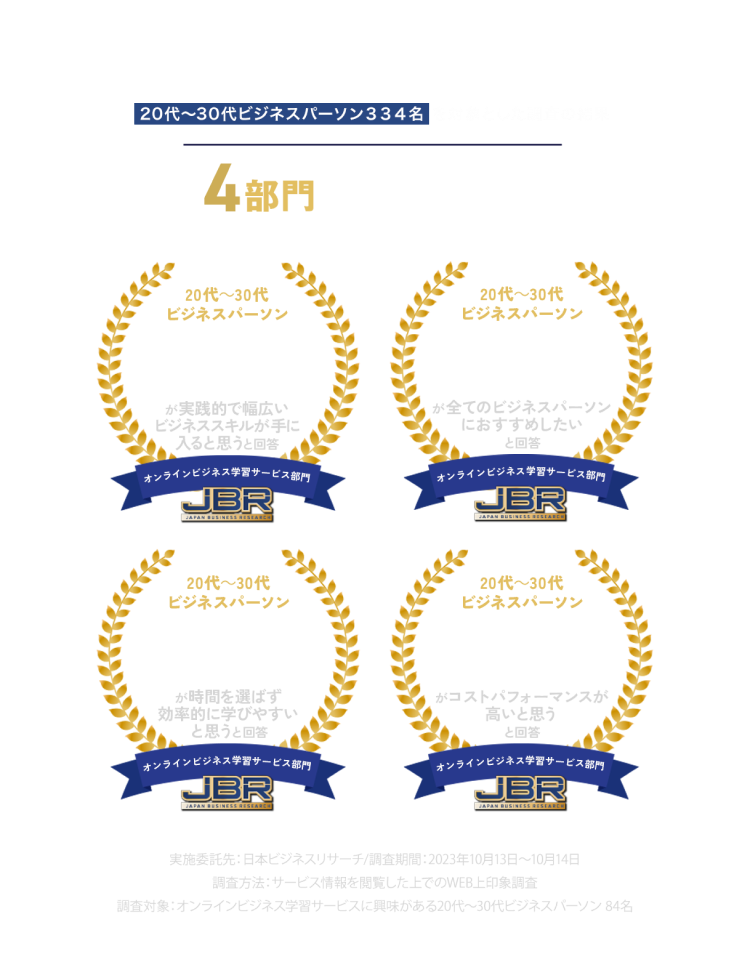

より理解を深め、他のユーザーとつながりましょう。
100+人の振り返り
shimada_takumi
金融・不動産 関連職
ミレニアル世代を中心に所有ではなくシェアを志向しているという意見があるが、これは間違っていると感じる。正しくは所有ではなくシェアをするのが合理的かつ現実的に取りうる唯一の手段になりつつあるため、シェアすることを受け入れざるを得ない環境に適応したということだと考える。理由は3点ある。1.税および社会保障負担増による可処分所得の減少で、高額な商品を購入するという選択肢取りにくくなりつつあること。2.賃金の上昇が見込めず、将来的にもそれは改善される見込みがないという意識が醸成され、ローンを組むことに対する拒否感が生まれていること。3.スマートフォンが万能のデバイスとなり、大抵のものは安価でそれなりの性能のものが手に入るため物に対する渇望感や購買意欲が生まれにくいこと。なおこれは大都市圏に居住する若者特有のもので、地方に関してはこの限りではないと肌感覚だが感じる。
hiroya14
IT・WEB・エンジニア
クラウドファンドは、お金のシェアという考え方なのですね。シェアという考えではなかったので勉強になった。お金こそ動いていない期間が多いので、もっと世界でシェア出来る仕組みがあればおもしろいかも。
satoho
建設・土木 関連職
相互評価の仕組みについて、客観的な判断基準の提示や仲裁機関の設置が不可欠だと思います。メルカリの一部ユーザーにように、売り手に無理な要求を突きつけ、それが通らない場合に評価を下げると脅す、といった行動に対し、有効な対策を打つことがまず必要だと思います。
mama25994
経理・財務
コロナ禍において、シェアリング・エコノミーがどう進展するのか、興味を持ってみています。阻害要因(他の人とモノをシェアすることで感染リスクが高まる)がある一方、進展要因(外食控えによるUber Eats やレンタカーの利用向上、等)があるのかと思います。
test_
メーカー技術・研究・開発
資産・労働力などの効率的な利用という点で非常に優れた考え方だと思いました。
一方で、将来はその人の信頼度が何らかの形で確認できるようになり、信頼が一度低くなると、誰からも相手にされなくなる。。。。そんな怖い世界を想像してしまいました。
atsumori_09
その他
シェアリングエコノミーの風潮が高まると、既存の業界での売り上げや利益減少が予想されるため、従来とは違った形態での事業を見つけないと、存続が難しくなると思います。
また、コロナによる生活様式の転換期にある中で、新たな体験・価値の提供できる体制を築けるのは、既存企業なのか、新興企業になるのか、気になります。
chihiro_mihara
経営・経営企画
昨今のコロナ影響で働き方や考え方も大きく変わりました。限られたリソースをどう使っていくか、すべての人の課題だと思います。
sugasyo
営業
エアビーやクラウドファンディングなど生活の中に入り込んでいる事がわかった。
saito-yoshitaka
メーカー技術・研究・開発
エコな時代と ビジネスモデルの変化対応は各企業の死活問題とも言えそうです。
hiroko-223
経理・財務
事業部が保有している遊休資産設備などをリスト化して共有財産として活用方法を考えるなど、可能性が広がる。
ken_mae
その他
組織の中で、自分の利権を守ろうと情報やコネクションを抱え込む人はまだまだ少なくない。どうしても譲れないものは仕方がないが、シェアリングの意識を持ってもっと組織や社会の発展に貢献しようという気運を高めたい。
wkiymbk
IT・WEB・エンジニア
「遊休資産の共有・売買。相互評価によって信頼関係を蓄積」が要点であることを学べました。
知識は顧客との会話、職場での雑談・ブレストで活用します。
paku_mogu
経営・経営企画
ミレニアル世代がシェアすることを好意的に捉えているとの表現がされていたがこれは誤りかと思う。
サービスを利用するために仕方なくシェアという選択肢を取らざるを得ないというのが実情。要は所有するほどの資金がないのです。
つまり人々が貧しくなることでシェアリングエコノミーが発展していきますが、とても前向きな話とは思えません。
kameco
販売・サービス・事務
質屋さんなどはシェアリングエコノミーかなと思いました。大昔から身近に存在していたのですね。
toshiyuki_chiba
メーカー技術・研究・開発
シェアリングエコノミーにはNFTのスカラーシップの考え方を流用すべき。
それを実現するにはまず財閥や大企業エコシステムの解体から始まるがね。
fusyoryokato
専門職
教育技術のシェア
ryo_murakami
メーカー技術・研究・開発
メンテ費用も含め割りに合わないものをあえて所有することはないだろうなと80年代生まれだけど思います。
djmpajmpkm
営業
まだまだ法の整備が追いついていないと感じた
macoki
販売・サービス・事務
シェアリングエコノミーは、まさに時代や価値観の変化の中で生まれたサービスだと思う。
今後、品質の維持やトラブル回避のためのルールが定まっていけば、さらに拡大する可能性がある。一方で、サービスがスタートしすでに7年ほど経っているにもかかわらず、トラブルが絶えない状況である。早急な法整備が必要だと思う。
ga_0608
クリエイティブ
普段見聞きしているしている事にシェアリングサービスが存在している事がわかった。面白い考え方だと思う。
shizuka_8
資材・購買・物流
近頃、ライバル企業同士がタッグを組み環境対応等を進める話題を耳にします。企業間でもビジネスの競争、ではなくビジネスのシェアが必要になってくるかもしれないなと感じました。
arisawa_kg
営業
メルカリ・ヤフオク等が身近な例ですね。余分にモノを生産することが減れば、エコにも良いですね。
shogo-
金融・不動産 関連職
法人のお客様への提案
shu-hirayama
金融・不動産 関連職
どのようなシェアが考えられるかを検討する
yoko_nh
その他
知識の蓄積、普段のメンバーとのコミュニケーション
asao17
IT・WEB・エンジニア
必要なサービスやスキルをシェアできるのは有効性があると考えるのはもちろんのこと、今からすぐ1時間このサービスを利用したいといった状況などに対応できるスピード感も重要だと感じた。
noriume
営業
自分の業界でシェアが進んだら、と考えるきっかけに為りました。自分の勤務先だけでなく、自分がユーザーになっている業界でシェアが進んだら、と考えながら利用したい。
takayuki0730
経営・経営企画
車や駐車場のシェアリング等は日常生活で見ますが、稼働率を高めるという事がひとつのポイントでしょうか。
sphsph
メーカー技術・研究・開発
世の中の流れをしっかり認識し、積極的に関わる必要性を感じた。
あらゆる可能性を視野に入れつつ行動する。
cier
メーカー技術・研究・開発
スキルのシェアは今後更に発展していくだろうと感じた。
taku_0318
コンサルタント
シェアリングエコノミーに主立って「空間」「モノ」「スキル」「移動」「お金」があり、基盤としての「技術革新」「所有に対する意識変化」「エコ意識の向上」があるが故に広まっているのだと学んだ。ミレニアル世代であが、将来的には車を購入したいと考えているため車のシェアは利用者としては現時点では考えていないが、オーナーとして利用することはありかなと思っているが、留意点や課題部分を吟味する必要があると考えている。
wata_hello_711
メーカー技術・研究・開発
脱炭素社会や再生可能エネルギーの活用等、既存のものを活用する時代の風が吹いていると感じた。
masarukanno
マーケティング
まず自分でなにかシェリング・エコノミーを利用してみたいと思います。価値観の変革を自ら体験してみようと思います。
yhataya
資材・購買・物流
業務の専門性を高めれば、社内でスキルのシェアができるような気がします。そうすると、部門の壁を超えた交流が生まれて、新しい働き方に繋がると思います。ちょっとモヤモヤしていますが、アイデアを発展させたいと思います。
mkyoshi
メーカー技術・研究・開発
シェアリング・エコノミーという観点では、単純にモノのシェアだけだなく、スキルなど無形的なものに関しても対象になっている点を改めて認識しました。
knhk
営業
今後日本では人口減少が加速していくので、シェアリング・エコノミーの重要度は増していくと思う
既存の業態のままだと取り残されると感じた。
301434
営業
高額使い切り商品を複数社もしくは、複数の顧客でシェアできるサービスや良いと思う。
リゾート会員権やゴルフ会員権等もシェアできれば使いやすくなる。
sota0501
営業
わかりやすく、何度もでも見返したい。シェアサービス、昔は図書館があたると思うが、常に考えながら生活していきたい。
noz
人事・労務・法務
持たないミニマリストがに関心が高まっているので興味深い
shibuya_01
メーカー技術・研究・開発
シェアリング・エコノミーなどの環境変化が自部署にどのようなメリット、デメリットをもたらすのか考えながら、仕事に取り組む。
matsu1009
営業
シェアリングエコノミーとは広義の意味があることがわかった。
suginoryu0502
営業
シェアリングサービスを活用していきたい。
maruyamatoshihi
営業
身近なところから何か有効に出来ないか、意識して取組むことが大事だと思いました。
hagimotsu
専門職
モノを作る仕事をしているので、モノの売上がへるのでは?と、
正直とまどう自分がいるが、まずは自分の中の意識変革のきっかけとして、この学びを活かしていきたいと思います。
chidori-nobu
人事・労務・法務
相互評価については評価者の精度も問われるため、更なる仕組みの構築が必要と感じた。
rx701sksf
マーケティング
自動車業界はまさにUBERを筆頭としたライドシェアが台頭してきている。これを危機として捉えることもできるが、所有と共有に用途が増えたと考えることでこれまでどちらかしか利用していなかった消費者に両方で使ってもらえるチャンスでもある。
「所有から共有へ」ではなく「所有と共有へ」につなげたい。
yamasma
その他
シェアリング・エコノミーが出来るアイデアを考えてみる。
guccigucci
経営・経営企画
一問目がよく理解できなかった。
user-df919bdbfa
undefined
自宅の高級品や車のシェアリングを試してみたり、シェアリングに有利なスキルを調べてみようと思った。
gokusi
販売・サービス・事務
Uber利用時考えてみようと思います。
justin1018
コンサルタント
クラファンがここに含まれるのが意外だった。余剰資産に着目すると面白い発見があるかも。
usamaru
経営・経営企画
個人に依存するビジネスのため、倫理観の高さ、コンプライアンスへの
意識に差があるように思います。
それが顕著に出たのが、コロナ禍におけるマスクの転売ではないでしょうか。
企業がこうしたシェアリングビジネスを活用するときには、
依頼先が信頼に足り得るか、十分な調査が必要だと感じました。
sakiyam2
IT・WEB・エンジニア
スキルシェアによる効率化は小規模だが自分の管理下で実験的にやっており、明らかに作業効率の改善が見られている。すぐに、ビジネスに繋げられるとは思っていないが、シェアリング可能は物が無いか意識して様々なサービスを見ていく。
masa_0125
IT・WEB・エンジニア
これからの時代、何をシェアするかを考えればビジネスチャンスがあると思う。
rinko_4343
人事・労務・法務
日常生活や仕事を通して、シェアリングエコノミーに活用できそうなモノやコトになりえるか?を常に意識していると、面白そう
kenichi-endo
営業
「所有」対する考えが世代により変化している背景が大きく作用している。
akira_okano
メーカー技術・研究・開発
ウーバー、AirB&B、Times24イメージだったが、「遊休資産の共有売買」と定義すると、メルカリやノマド、クラウドファンディングもシェアリングエコノミーに含まれる、というのは今まで考えていなかった。
75475
メーカー技術・研究・開発
個人ではできないことの実現や費用節約に役立つ。
c2
メーカー技術・研究・開発
日常的にフリマアプリを使用しており、名前も顔も知らない取引相手の信頼性をいかにして把握できるようにするかがシェアリングの中で重要と感じた。
soul-kitchen
営業
人材不足を補うための一つの手段となるものである。
fieldmouth
金融・不動産 関連職
カーシェア、ルームシェアが一般的になってきたが、更にいままでの既成概念を超えたシェアが一般的になることを考える必要がある。
otaru
営業
時代変遷と共に所有から利用への価値観変化を受けたビジネスチャンスが有り、ユーザー視点で判断基準を持つ事が一層求められる
ta_d
営業
コロナでオフィスの固定費が注目されたこともあり、シェアオフィスや貸し会議室へ移行するかと思われる。固定費の負担が大きいものやことを対象にシェリングエコノミーがより進みそうである。
ryoken
専門職
新しい発想の変革が必要である。
clover_0507
経理・財務
所有にこだわらない人はますます増えると思う。将来のビジネスの可能性を探り続けることが大切だと思う。
so-hei
建設・土木 関連職
借りれる技術は良い面もあれば成長意欲が欠如するなどデメリットがあると思うので会社の利益となり、成長もできるバランスの取れたシェアが大事かもしれない。
penguinqueen
その他
意識の変化、技術の進歩を考えると、既存産業とは異なる発想での事業が増加し、そこにビジネスチャンスがあるという認識に立ちました。
koji_niwa
人事・労務・法務
長期のコロナ禍での働き方の変化により従来のオフィスやクルマの在り方を見直すきっかけになりました。
tttttooooo
営業
遊休資産を活用するときに有効だと思います。
user-58058239f7
営業
新しいビジネスの芽が出る可能性が高い。当社の取引先の候補もあるかもしれない。
nhgngsk
営業
日常に当てはめにくい
keyaki_123
IT・WEB・エンジニア
ここ数年でシェアリングサービスが身近な存在となってきた。必要な時に利用するというのは、利用者側と提供する企業両方にメリットがありそうだが、車や家電などあらゆる産業で売り切る型のビジネスが成り立たなくなってくるのではないかと思う。物が売れなく、如何にサービスで稼いでいくか考えていく必要がある。
arisa0529
営業
解決
yoshikawa0521
専門職
シェアリングエコノミーについて正しく理解することができた。
tarabkin
営業
全体的に、「ムダを省く」という意識が根っこにあるように感じた。
matsudatt
メーカー技術・研究・開発
モノの所有という価値観が大きく変わってきたことが大きいと思います。それにプラスして、テクノロジーや生活の変化が後押しをして、活況になっています。
masuda9000360
経理・財務
・企業には多くの遊休資産・遊休予備資産があり、シェアリングの発展は日本経済全体で有効と考える。
・機会損失を回避するため、営業マンに1台ずつ営業車を付与していたが、カーシェアの発展で、その必要性は薄まった。
reiwa
メディカル 関連職
わかりやすかったです
kouhei728
経営・経営企画
意識などの価値観の変化が大きな要因と考えている。従来は所有こそがその人の価値であったと思います。
良い家を持っている。良い車に乗っている・・・など。
この価値観が変化することによって必要最低限の資産を持つことによる適切なコスト意識も芽生えると思いました。
yaoshi
メーカー技術・研究・開発
シェアリングエコノミーはいろいろな場面で目にすることができる。
利用者側だけでなく、個人の空き駐車場など新たな設備投資なしに参加可能なものであれば、資産提供側としても活用を考えたい。
yuuu
営業
メルカリやウーバーなどと「シェア」の考え方をつなげることができた。今後もこの視点でもイノベーションを考えてみたいと思った。
aezy
営業
ものが溢れている今の時代、物を買いたいという意識よりも、今所有している物の価値をいかに高めるかという意識に向かうのではないか。
所有しているものを有効活用(現金化)したいというニーズはさらに増えると思う。
手軽にそのニーズを満たしてくれるサービスが今後伸びていくのだと思う。
to-taniguchi
メーカー技術・研究・開発
メルカリやカーシェアなどが流行っているのは知っているが、自分自身利用したことがなく今後もする気がないため具体的な想像がしにくい。やはり企業が提供する安全性の担保は重要だと思う。
cizawa
経営・経営企画
モノやサービスを対象の顧客に提供するビジネスの考え方から、共有する、つなぐことでビジネスを行う考え方に幅を広げることが必要なことを認識した。つなぐ、共有することでコミュニティに加わり、そこからまた別の機会領域にてんかいしていくことが必要だと思う。
y-fufu
メーカー技術・研究・開発
個人の持っているスキルを社内にアピールする場がもっとあると良い。
tanakahiro
経理・財務
自身のスキルを磨くことで新しい収入を得ることにつながる可能性が高くなっている。過疎地で生活する際に大切な収入源になるかも。
ishida_m
IT・WEB・エンジニア
人口減少が進んでいくことを考えると人にしかできない分野において労働力のシェアはとても重要だと思いました。
また、スキルをシェアするという意味では、自分自身の価値を示すことにもなるので、継続してスキルを向上させていきたいと思います。
ryosexy2
営業
シェアリングエコノミーが普及していくと、日常生活が180°変わるくらいのインパクトが出ると思う。この潮流に少しずつ慣れていかないと、生きていけないくらいの危機感を感じた。
と同時に、非常に効率的で自由な社会になると思うので、その社会を守るためにも、個人情報管理や保険などのリスクマネジメントを法整備を通じてしっかり守ってほしい。
neo210515
メーカー技術・研究・開発
シェアリングサービスの特長、課題も理解できる一方、きちんとした製品の方が安心感がある、所有欲が満たせる、サポート体制が充実しているなどのメリットもある。一概にどちらが良いとは言い切れず、TPOに応じて判断していくことが必要になってくると思う。
yabu45
メーカー技術・研究・開発
自然と自分もシェアリングエコノミーに参加していた。価値観の変化など踏まえてさらに理解したい。
genta2020
IT・WEB・エンジニア
提供者と利用者の相互評価が重要ですが、買い物サイトのステマレビューや同業者からの嫌がらせなどと同じことが発生しそうなので、正直怖いなと感じました。
may55
経理・財務
安全性を確認した上で、上手にシェアリングできればと思います。
japan5515
営業
スキルのシェアサービスに魅力を感じました。
gantaroimo
その他
シェア可能となる対象が増えていくと思われるため、情報収集を行い、新しいアイデアを考えたい。
cyobii
金融・不動産 関連職
なかなか共有には抵抗がある
ジェネレーションギャップだろう
amano_048001
資材・購買・物流
シェアリングエコノミーの発展と事業への展開は自らの発想の転換が必要になりそう
hayato-tizu
販売・サービス・事務
お金は銀行から借りるものだ→クラウドファンディングで集めるもの
車は所有するものだ→使いたいときに借りればいい。
既存の価値観・考え方をしていたら令和の時代では通用しないビジネスマンに
なってしまう。
自分の働いている業界が今後どうシェアリングが行われていくのかを考えて
見たいと思った。
sk_2020
営業
オーバーラッピングした資産を共有する際には、展開ビジネスの4P面での差別化できると面白く感じます。
omokun
経営・経営企画
遊休資産という概念を考えた事がなかったので、勉強になった。
カーシェアもだんだん普及しつつあるのでやってみようかな。
yuko625830
営業
営業業務に活用できると感じた。