こんな人におすすめ
・自身や組織の働き方に関心のある方
・働き方改革の背景を知りたい方
・働き方改革を実行している組織の事例を知りたい方
このコースについて
2016年の「経営トップによる働き方改革宣言」に加え、2020年からのコロナ禍も相まって「働き方改革」が身近になった方も増えてきたのではないでしょうか。
一方で、働き方改革が進んでいても社内ルールの背景は正しく周知・理解されていますか。
本コースでは、働き方改革がもたらす効果として期待されることとは一体どのようなことなのか、背景とあわせて説明します。
また、テクノロジーをうまく活用しながら活動を推進した事例として、Googleが実施した「未来の働き方プロジェクト」の参加企業に、改革を推進する上での難所、それを乗り越えるコツについてお話しいただきます。
自身や組織の働き方を変えてみたいと考える方はぜひヒントにしてみてください。
講師プロフィール
グロービス経営大学院 教員
林 恭子
グーグル合同会社 ブランド&サーチマーケティング統括部長
Women Will プロジェクト統括
平山 景子
広島県 総務局業務プロセス改革課 主任
酒井 進
コクヨ株式会社 ファニチャー事業本部 マーケティング本部 働き方改革チーム チームリーダー
髙橋 大
(肩書きは2017年8月撮影当時のもの)
コース内容
- コース紹介
- 日本企業、日本社会が抱える働き方の課題
- 未来の働き方トライアル
- 取組み事例
- 参考①Work Anywhereを実現する6つの行動
- 参考②Work Simplyを実現する6つの行動
- 参考③Work Shorterを実現する6つの行動
- 参考④Work Life Balanceを実現する4つの行動


















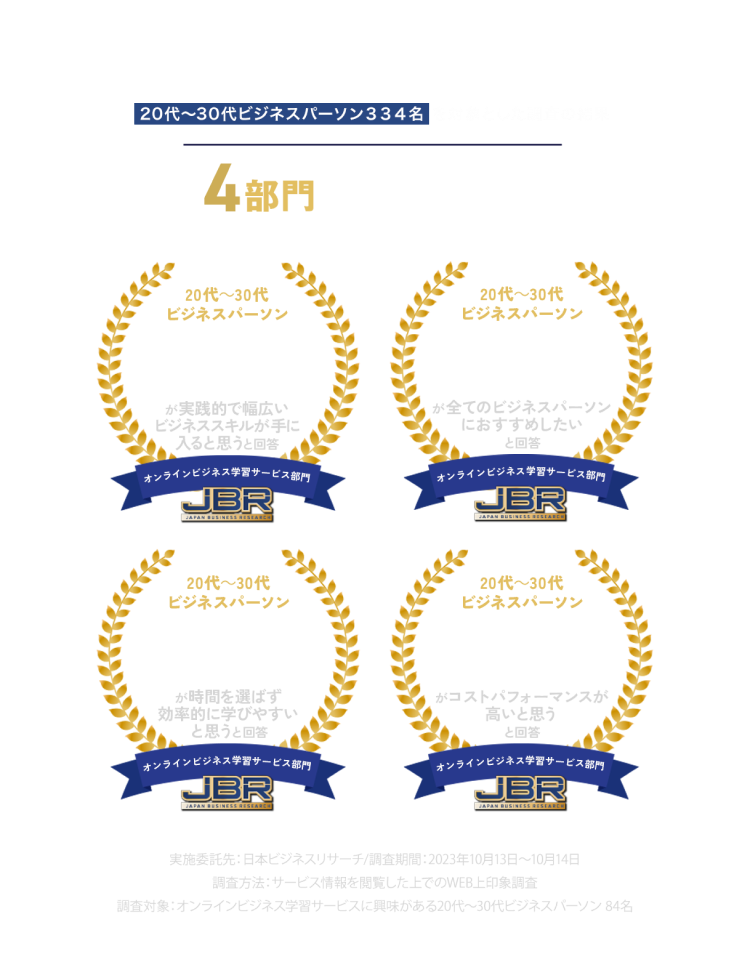

より理解を深め、他のユーザーとつながりましょう。
100+人の振り返り
eh10
IT・WEB・エンジニア
働き方改革を行う必要性を全く理解していなかったので、大変勉強になった。
独身で子供がいない私には全く関係のないことだと思っていたが、今後自分が介護をする可能性があること、そうでなくても国全体として取り組むべき課題であることが理解できた。我が事として考える必要があると思った。
弊社の場合、部門リーダーが「個人情報を社外で扱うのはNG」の一点張りのため、リモートワークを行うことが出来ない。これは、部門リーダーが働き方改革の必要性もテクノロジーのことも理解していないからではないだろうか?
これを変えていくためには、人事部門とIT部門の両方からのアプローチが必要だと感じた。
個人としては、スケジューラーの入力を早速実践している。頻繁に横やりが入るため、中々予定通りに事が進まなく、その分が残業時間に繋がっていることがわかった。
上手い時間の使い方を考える必要があると思っている。
kenji364
営業
効率よく働くということは、自分一人だけではなく、みんなと協同しなければ、本当の意味での効率が良くならないことが理解できました。
shirokuma0224
IT・WEB・エンジニア
当社は2012年ごろから働き方改革に取り組んでおり、今回のコースの内容は
基本的に全て会社の常識としての意識形成が行われている。
比較的先進的な状況にあるのだな、ということを実感した。
とはいえ、理解&実践できているのは40歳以下の社員だけという印象を受ける。それ以上の世代は、部下や他者に対する理解はあるものの、
実践している様子はあまり見受けられない。
(実践することによる自分へのメリットはあまりない、または、
多様な働き方を社員に促すために、自分は会社に長時間留まって有事に
備えなければ、というふうに考えている人が多いし、家庭環境から
それがあまりストレスなく実施できてしまう)
それが、今回のコロナによる在宅勤務で大きく変わり、今後会社が
更にどのように変化するのか楽しみだ。
junichi-78
経理・財務
在宅勤務活用については、事務職と現場(特に製造業)では根本的な違い(活用可能の可否)があり、本テーマについては事務職あるいは営業職限定になるのではないか(製造工程、作業工程のロボット、IOT化が相当進めば別だが)と感じました。
ayachobi
人事・労務・法務
自社でかなり実践していることばかりでした。スケジューラーでの業務内容記入や、在宅勤務時の始業終業の見える化、フレックスの積極的な活用など。
しかし、こうしたことは私の職場では当たり前のようになっていますが、部署によっては違いがあるようにも思います。やはりその部署のトップの考え方や姿勢の影響も大きいので、会社全体で推進するには部署のトップの意識改革が必須と思います。
toru9012
営業
働き方改革と言うとハードルが高く感じるが、Work Anywhere、Work Simply、Work Shorter、Work Life Balanceを意識することで、自分自身の仕事の効率化にもつながっていくのではないかと感じた。
patricia_2020
その他
詰まる所、昭和的男性中心の意識改革を行うことによって働き方改革へ繋がるということですね。
yohe524
営業
働き方改革最近流行っているが具体的になにお取り組めばいいのか明確に理解している人は私の会社では少ない。単純に残業時間を減らせ等言われるがどういった取り組みをして減らすのかトップから明確に降りてこない。今回の動画では同具体的に取り組むのかがわかる内容であったので学んだことを活かして自分での職場での働き方改革に活かしていきたい。
miura2081
営業
すぐに活用できる内容が多く、非常に有用でした。特にスケジュールの共有と、ルール作りのところが参考になりました。メンバーが取組易い様にメリットを伝えて取り組みたいと思います。
また、いずれの取組も、意思を持って継続的に行う事が重要だと感じました。
user-7d67232fe9
コンサルタント
googleさんすごいっす。
働き方改革を「パフォーマンス」で終わらせない感じがすごいっす。
事実、働き方改革が自分たちにとって都合のいい形で運用され、徹底されない場合は効果が半減してしまう危険性もある。
「自分たちの職場に合った」という個別の事例ごとに当てはめる工夫ももちろん大事ではあるが、目的を十分に達成できない程度まで妥協をしてしまった場合、有名無実化してしまう。
googleさんの働き方改革セミナー受けて、意味ある改革を実践したいものだ。
提案してみようかしら。
watana
メーカー技術・研究・開発
クラウドを利用することによる働き方改革を実施すること。それをメンバに伝え、考え方も変える必要があることがわかりました。
pepsiman
専門職
COVID-19の影響で初めて在宅勤務を実施した。ほとんどの業務が在宅でも実施できるし、オンラインも積極的に活用できた。
また、通勤時間が無くなり、時間を有効に使えるようになった。
sayan_
メーカー技術・研究・開発
残業しないで帰るのが当たり前の職場を目指したい。夫が長期出向で子供がいる女性が会社を辞めてしまうことが残念。他にも自分の意志以外の理由で退職する人を何度も見てきた。ツールを積極的に使って、多様な人が職場に残れることを証明していきたい。
hiro_yoshioka
メーカー技術・研究・開発
ITツールやスケジュラーの使い方など 具体的なコツがわかりました。
家族でもスケジューラーやデータ共有を駆使するのはいいですね。
そういう時代なんだな。。と、ツールを活用してついていこうと思います。
振り返ってみると、
会議の議事録や、進捗確認の時間、資料やデータを探す時間
など、現状、まだまだ減らせそうな無駄が多いことにも気づきました。
実際に使ってみないと、気づかないことが多い。
まずは、自分がどんどん使ってみることからですね。
スケジューラーに「P」をつけるは、明日から早速やりますw
情報公開や共有による効率化は、情報リスクと表裏一体とも言えるので、
このあたりをケアできるツールがどんどん出てきてほしいですね!
yamada_5000
営業
選挙と同じで、一人一人が当事者意識をもって取り組むことが大切だと感じました。
mokumintosan
メーカー技術・研究・開発
管理者の自分だけが働き方を改善するだけでは、組織全体のパフォーマンスアップにつながらない。
まだまだテクノロジーを活用した効率化ができていない。
このレッスンビデオはよくまとまっており、効率化の気づきがたくさんあった。
組織内に周知したいと思う。
moocaster
営業
働き方改革の意義を知れてよかったです。労働人口がこんなにも減るとは知りませんでした。もっと働き方改革を知って、皆が自分事のように捉えることが大切です。
t17
その他
まずは、実際に使ってみて、経験談も取り入れて効率化について皆で考えること。結局は、皆で効率化を目指さないと真の効果は得られないと分かりました。
edueduedu
販売・サービス・事務
事例が分かりやすく、参考になった。所属する会社では、在宅勤務の制度はあるものの実際に使おうとすると壁があって使えず、上部層こそ意識改革・働き方改革に取り組んでほしいと感じた。
takeshi4413
メーカー技術・研究・開発
コロナ禍で、働き方改革が急激に進む結果となったが、特に今回の中では、Work Simplyの会議の効率化の中で、学ぶ点がまだまだあると思った。(決定事項とアクションアイテムの明確化や議事録の共同作成など)
一方で、帰宅時間をスケジューラーで明示するだけでは突発的な依頼は無くならない気がしました。やはり、業務自体をもともと計画に進められるような工夫をもっとしなければならないと思います。計画通り進めば、計画が立てられると思うので。
yuki_0719
マーケティング
世代による仕事観の違いを理解できた。自分の経験してきた働き方を是とせず、組織メンバーそれぞれの仕事観を理解した上で、マネジメントすること、いかにモチベーションを高めさせられ、生産性アップに繋げられるかの視点が重要と感じた。
katsu_731
資材・購買・物流
Googleでの実践トレーニングのナレーションのスピード感で更に効率性を感じた。会議中の議事録同時作成はまだ取り組んでない。特定の一人が議事録担当だと、聞き取れなかった、判らない用語がある等で作成に時間が掛かる。やはりその発言内容を一番知っている各発言者が発言直後に、ポイントだけ書けばそれでOKといルールにすれば良いと思った(発言する前に話す内容が決まっていれば、予め書いておくこともできる)。
kudo0512-hoko
マーケティング
グーグルの宣伝ばっかで時間のムダです
wkiymbk
IT・WEB・エンジニア
データとスケジュールの共有、またそれを推進するツール・運用の整備が肝だということがわかりました。
自身はこれらをすでに活用しており、今後も継続します。
kzhr2358301
金融・不動産 関連職
メンバー間のコミュニケーションの取り方、スケジュール管理から、働き方改革を進め、生産性向上、効率化につなげたく思います。
katsu_c
メーカー技術・研究・開発
色々参考になりました。成果を効率良くあげるに尽きます。働き方改革以前の意識改革も必要だと思います。
noda_1108
メーカー技術・研究・開発
個人用と会社用とスケジューラーに入力することで凄い時間を取られそうです
ishida_m
IT・WEB・エンジニア
働き方改革にはトップや管理職の理解が一番必要だと思います。
現在はコロナの影響もあり在宅ワークを実施しているが、落ち着いてきた時は出勤率が高くなっていたので、一時的なものにせず継続していければと思います。
社員全員の意識をそういった方向へ向きつつあると思うので、もっと色々な改革を進めていきたいと感じました。
matsu1210
経営・経営企画
毎日の予定作業内容・必要時間・作業したい時間(がんばるタイム)・移動時間などを具体的に書きこむ、周囲の人に今何をしているのか共有することで、コロナでテレワークが継続している現在だけでなく、出勤が当たり前になった際のチームの業務量や所要時間を確認しやすくなると思いました。また自分がこんな業務にこんなにもの時間をかけているということの見える化にもつながるので本当にセルフマネジメントが重要だと思いました。
(記憶に残ったこと)
・週に1回定例で事前に入力する。会議なのか作業なのか出張なのか移動なのか、連絡可能時間などを含めて詳細に記入する。予定退社時刻も記入する。さらにプライベートな予定があるならPマークを使うなど、チームのみんなで共有しやすい符号とする。
・定時に帰るためには本人のマネジメントだけでなくそのための上司のコミュニケーションも必要。
maytokyo
マーケティング
Google ツールの活用いいですね。 仕事のみならずLifeでもスペースを創ることでより余暇の時間の充実を図れるように思いました。 事例紹介では企業のみならず自治体での活用事例もあり素晴らしいです。 もっとGoverment関連の組織での働き方改革必要ですね。 ありがとうございました。
zico10
経営・経営企画
ちょうどコロナの影響で勤務先の働き方改革とリモートワークが進み1年間位が経過するので今の現状をチェックする意味で大変参考となった。特にスケジューラーに打ち合わせだけでなく、To Doも備忘録・自分の作業時間確保と検証のために
記入しているのだが、Googleも推奨しているので安心したし、それなりに対応できていることを確認できた。一方、家族対応にも同じことが言えるので、早速スケジュールは家内と共有化していきたいと思う。
hideo_furuta
メーカー技術・研究・開発
働き方改革は、やらされ感が強いですが、メリットを知って活用することで働きやすくなると理解できました。
oy_ko
その他
実践してみたい工夫がたくさんあった。スケジュールの共有は聴講したその日から実践してみている。
mon-chan
資材・購買・物流
まずやってみる、というのは大事だなと思った。考えるだけだとネガティブな思考(課題は何か、どうするか)が頭をよぎるばかり。やってみたら意外といいね、となる可能性はあるし、会社にあったやり方が見つかるはず。ただし、柔軟な対応が取れる体制が必要。
kairikokarin
販売・サービス・事務
制度としてはあったものの、新型コロナウィルスにより結果的にではあるが実際に在宅勤務が始まり1年となる。会社でセキュリティ対策のあるネット環境を構築してくれていたためスムーズに移行でき、スマホとPCがあればTEL・メール・チャット・ビデオ会議で仕事が進められ、働き方は大きく変わった。コミュニケーション上の課題を感じることはあるものの、時間の使い方の自由度が上がるなど、全体的にメリットを大きく感じている。
sevastian
営業
こんな世の中ですから、嫌でも在宅勤務を積極的に導入すべきかと思います。また様々なツールを活用する事で効率を上げる事ができるかと思います。特に共同編集作業の部分は興味深いと感じました。
_macky_
メーカー技術・研究・開発
1日30分でも早く仕事を切り上げることを意識するだけでも随分変わる。
現在の職場はある程度テレワークなど実施できる環境にあるため、まずは小グループ単位でトライを実施して、広めていきたい。
ys-0184242908
専門職
在宅勤務を有効活用していくためには,ペーパーレス,ハンコレスをこれまで以上に進めていく必要があると感じた。
aki_100
経営・経営企画
ツールは揃っているので、具体的に実績するのみだと思いました。スケジューラーに予定を書き込む、帰宅時間を書き込むなど、習慣化が必要なことを以下に地道に粘り強くやっていけるかがまず必要なことですね。
kameco
販売・サービス・事務
私は現在、コロナ対策の一環として在宅勤務を利用していますが、このままずっと利用したいです。始める前は確かに不安がありましたが、実際にやってみるとそんなに不便はありませんでした。自分の作業を見つめ直す機会にもなりました。ただ、システムや機材管理や貸し出し、メンテナンスやサポートなどを担当してくれる部署はとても大変だったと思います。
bignight
IT・WEB・エンジニア
日本人の生産性が低い くだりがありますが、日本人の生産性が本当に低いのかの議論が あります。
ここで「日本人の生産性が低い」を使うことは 如何なものか?と思います。
audi2005bmw
金融・不動産 関連職
コロナ前の動画をコロナ禍3年後に見ると感慨深い。この3年で当社でも相応に働き方改革が進んでいると実感させられた。
ichi_02
金融・不動産 関連職
インフラやトップに関わるところはともかく、自分でできるところから始めたいと思う。
スケジュールに関して、突発事項で内部のことに言及され、「スケジュールを共有して振らないようにする」はその通りだが、突発事項はアクシデントや顧客、他社・他部署等情報を共有していない関係者からもたらされることが多いため、そのような場合の管理方法も考える必要があると思う。
「生産性向上は全員で」ということなので、じっくり考えるという考え方はもはや受け入れられないということか。
※Work Shorter のビデオで、進”捗”が進歩(手偏なし)になっていました
hi-hayashi
IT・WEB・エンジニア
夫婦の仕事関連やプライベート関連を、スケジュール共有することで家事や育児の分担の効率化ができるのは、とても良い施策と感じた。
情報過多の昨今、必要な情報や有用なツール(アプリなど)の選別に力を注いでいく時代になったのだと、改めて認識しました。
tsuyoshi-n
営業
まだまだ会社に行って仕事をしたい社員が多いように感じます。そのボトルネックをヒヤリングしつつ、使えるツールに置き換えながら実践してきたたいと思います。
omokun
経営・経営企画
ITツールを駆使することが、仕事でも家庭でも効率化を生む。
特に共有スケジュールや共有データは必須。
yustrike200
営業
コロナを受けてリモートワークがかなり促進されました。
事前のルール決めもままならなかったのですが、その中でも日々
メンバーとコミュニケーションを取り、新しいワークスタイルを探しております。
morix2
その他
諸々の共有を行い、同質の同僚がいることでフレキシブルな働き方ができるのだろうと思う。また、管理職の場合、任された組織への責任を負うので、まさにトップの意識が講座で示されたように変わらなければならない。
最近、時短が進み仕事の質が下がっているのは気になっている。短期的には仕事は回っているので良いが、長期的に質を維持できないのではないかと危惧している。例えば文章の推敲が不十分で誤字脱字の散見、意図が伝わりにくい構成、分かりにくい文章がそのまま仕事の成果となっている。これまで時間をかけることにより解決されてきたものが、解決できなくなるのではないだろうか?一人一人の働き手としての高度化が必要な時代だと思う。
toshio11
金融・不動産 関連職
働く時間を短くするため、全員の意識を共有する事、ツールも適切に利用することが大事。
yaski
営業
良いと思いますが、プライベートまでスケジューラ管理するのって、少し抵抗感があります。全てが同一プラットフォームに乗っかるのも、、どうかと。
プラットフォーマー側に立てば、シェアを増やす事はHappyでしょうが。
saito-yoshitaka
メーカー技術・研究・開発
コロナ禍の影響で一気に在宅勤務が進み、環境も整いました。やらざる得ない環境化では同じベクトルを向き進むことを感じました。
andoh_m
メーカー技術・研究・開発
会議時間の短縮の方法を意識して取り入れていく
taka-p007
メーカー技術・研究・開発
会社では業務の効率化に取り組んでいるが、プライベートでは夫婦間の担当は曖昧(妻の方が圧倒的に多い)であった。
ツール活用により見える化する事で、ある程度のバランスを保てるよう努力すべきと感じました。
myukiko1007
経理・財務
テレワークは導入しており、我々が行っていることが
間違ってないな、と認識できた。
時間管理については、その日やることは決めても、
何時間で行うかを決めていないから、そこも決めてやってみようと思う
koba-h114792
建設・土木 関連職
コロナ禍明けで働き方の進め方も以前のように戻ろうとしている。メンバーの意識を確認しより良い仕事の進め方を検討したい。
hina0301
メーカー技術・研究・開発
特別な事情がある人のための制度と思われているものを、全員に一斉に取り入れてもらうことで理解を深めるのはよいと思った。急な事情で使うとなった時に、一度でも経験があるかないかで心理的ハードルが下がると思う。
taubou
メーカー技術・研究・開発
ITツールを駆使して働くのが、ポイントですね。
あとは、人間関係を良好に保っていきたいですね
muto10
販売・サービス・事務
いいたいことは分かったが、いまいち具体的な事例としてイメージできず、また、効果・メリットやデメリットが、よくわからなかった。
yamazaki_kohei
販売・サービス・事務
業務で活用するにはまず管理職の意識改革、そしてメンバーにも何故必要なのか、何がメリットかを理解してもらうことが重要と感じました。
nagata-1
営業
コロナ過以降、各社とも手探りで進めておられると思います。
弊社も進めておりますが、役職層・経営層の意識の統一はまだまだこれからと感じることが多々あります。
私自身は昭和な営業ですので、出社してのハードワークに生きがいを感じる場面もあり、
この点からも変えていくのが大切と感じます。
ibet
営業
プライベートも仕事も両方充実させることは可能である
morimotoa
営業
在宅勤務、業務時間短縮等、特定の人に負担が集中するものであってはならない。
take0526
営業
今の仕事のやり方を疑って、ゼロベースで考えることが必要。
今までの常識にとらわれない仕事のやり方を進めることは、コロナ禍ではますます不可欠となっている。
kei0415
経営・経営企画
仕事では「資料の共有」や「スケジュールの見える化」は実施できている。
やはり情報の共有が一番効率的ですね。
あとは「夫婦でカレンダーを共有」を実践して、妻も私もワークライフバランスをもっと改善したい。
hig11394
営業
会議の進め方やデータ活用などは疑問に思っていた進め方・やり方について答えを出せたと思うので参考になりました
yaruzo-
販売・サービス・事務
現在のコロナ禍により、テレワークが半強制的に始まり一般的に認知された感があるが、先を見ている企業はすごいと感じた。遅ればせながら、働き方改革を積極的に促進したい。
oliveoil_77
金融・不動産 関連職
グーグルの取り組みや、コンテンツ内容はまさにベーシックだが、それが同じ水準でできているかといえばそうではない。徹底すること、メリットを共有すること、見える化は、キーワードとして自分から率先したいと思います。
kanekc
人事・労務・法務
在宅勤務の抵抗はコロナ禍において、かなり意識改革が進んだと思う。
新しいものを取り入れる不馴れ感を、苦手と捉えないこと。
やってみよう!は大事。業務に取り入れていく、共有する、どう使おうか議論する。
とてもいい時間となっている。
araki_6384
営業
ダイバーシティ&インクルージョンによりワークライフバランスを進めるためには、夫婦の協力をもって、家事と子育て、そして仕事を分担することで成立するケースがあることをカルチャーとして根付かせることが大切だと感じました。
今までのカルチャーでは、日本は女性が管理職に就く割合が少ないことが当たりまえで、新たな価値が創出できいない可能性が高いと思いました。
これはグローバルという視点では日本は発展途上のように思います。
このコースで丁寧に学ぶことで、理解が深まりました。
daigo-hirano
その他
諸外国に比べ日本における「働き方改革」に遅れがあること、またその背景・要因について再認識することが重要。「働き方改革」には経営トップのコミットが最初の第一歩であることに加え、従事者一人ひとりの意識改革が重要だと感じた。まずトライアルを実践し、メリット・デメリットの共有、課題を認識することにより一歩ずつ「働き方改革」に向け取り組んでいきたい。
kei4319
メーカー技術・研究・開発
ワークライフバランス、そして少子高齢化の現実を考えれば今後は共働きが普通になってくる。しかし親の介護の問題等を考えると働き方が変わってくるのは避けられない。その中でいかに生産性を落とさない、むしろ生産性を高めるための働き方改革が重要であり、単なる働き方改革ではなく、生産性向上のための働き方改革という意味でGoogleが実践しているように仕事の高効率化は非常に分かりやすい。
yus_takahashi
建設・土木 関連職
簡単なことだけど実はできていない。そんなことに改めて気づかせてくれる内容でした。
特に会議に関わる人のコストと時間でこの会議がいくらなのか。それを目安としてでも図るのはとてもいいことかと思う。
とりあえず聞いといてほしいからあの人もこの人も同席させる。そんな会議がとても多いと思います・・・。(そしてアジェンダになく、思い付きで話し、そこからどんどん脱線していくことのいかに多いことか)
効率化、短縮化できていると思っていてもまだまだ改善シロを持っている会議は非常に多いと思う。
ymaaru
専門職
働き方改革の細かい工夫についても紹介されていたので実践してみます。会議の効率化は進めていますが、参加者で議事録を作りながら共有するなど試してみたいと思います。
kikuken
建設・土木 関連職
ワークライフバランスのコースを視聴して、夫婦の育児、家事も仕事の延長になっている時代なんだなあと、思いました。
家に帰ってまで仕事をしている、という環境が望ましいのかどうかは個人の価値観によって違うのかもしれませんね。
ike-day
IT・WEB・エンジニア
人口減少に伴う労働力減少への対策が必須であり、働き方の変革を通してその対処をしっかり着実にやっていかないとすごくマズイと感じた。周りがやっていなくとも、自らが率先して紹介いただいた事例を実践していくことで、周りの意識も変えていきたい。
asatake
その他
スケジューラーにチームメンバーのその日のスケジュールを記入してもらい帰宅時間も設定してチーム内情報共有化する。チームとしての業務効率化を進める。特に特定の人に偏っていないか確認できる。
yosdpal
マーケティング
様々な働き方改革を実践していますが、旧来のままの働き方を選ぶ方も一緒に働いているので、このカリキュラムを学んでいただけると仕事がしやすくなると思いました。
masa_0697
IT・WEB・エンジニア
効率的にというのは個人だけでなく全体で取り組まないといけないと改めて考えさせられました。特にこういう社会情勢なので、一人一人が意識して実践していこうと思います。
usajige
その他
Work Anywhere、Work Simply、Work Shorter、Work Life Balance
業種柄、すべてを進めるのは難しいものの、すぐにでも活用できるアイディアもあり、参考になった。
kuni1973
営業
最後のGoogle のトピック参考になりました。育児家事分担していきます。
igarashi-san
その他
働き方改革は実施されてきているが、まだ変わっていない方もいるのも事実である。
意識付けがとて重要と感じた。また実際にプライベートの時間が取れるようになったなど体感してもらうしかないのかな。。
sato-kaori
専門職
「共有」ということが、項目ごとに具体的に示されていた。このように行えば、様々な不安が軽減でき、進められそうに感じた。
hirokiii
営業
既に実践していることが多かったです。
個人の動きで変えれる事と、会社で取り組むべきことがあります。会社で変えようとし、方向性を作らない限り基本的には難しいとは思いますが、個々人の意識を変える事で全体を動かせると思います。
blueocean
人事・労務・法務
周囲に比べ残業の特に多い人は仕事を計画的に進めておらず目の前のことに忙殺されている感じがする。それは長期的にも、一日の予定でも。
仕事の「見える化」は改めて重要と感じた。そして、共有化も効果的であると思う。
77-k
その他
仕事のみならず、今を良しとせず、様々な視点で見直すことの重要性を学んだ。
y-c-challenge
専門職
個々のスケジュールの共有は自分と職場の仲間との働き方改革にとても有効な手段であることが良く分かった。
sa-t
営業
他社の事例を参考に取り入れてみる
c33
その他
在宅勤務や情報共有のさまざまなツールが整ってきていることを実感できた。
実施者の意識や感覚をそろえていくことで新しい働き方が実現できるだろうという希望を感じた。
enya-kazuhisa
人事・労務・法務
考え方が確認できれば、あとは自信をもって実践するのみ。自ら手本を示しつつ効率的な公私の時間の振り分けのバランスの追及を課内職員全員で取り組む
yamashita_koto
営業
内容が少し古いのか、オンライン至上主義的内容が垣間見られる。
現在は、オフラインでのコミュニケーションにも一定の必要性を認める意見が出ており、実際、「議論を必要とする」会議では、オンライン会議でやりきれない場合がある。
ただ、オンラインでできることが周知された効果もある。
常に新しいツールを活用し、いかに効率よく、働くかを常に考えることが重要。
marimati
メーカー技術・研究・開発
出来る事からやって行きたい。多様な働き方の中で組織の共有する価値観を高めることを目指したい。
stani
専門職
テクノロジーの進化で、仕事場だけでなくほかの場所で仕事をすることがかのうになった。しかし、育児や介護は人間相手なので、ソフト的な対応が重要となる。
seibu2023
メディカル 関連職
特にスケジュールの共有と、ルール作りのところが参考になりました。
今後、今回の講義内容を参考にしていきたいと思います。
horichan810
人事・労務・法務
自らのウィークポイントとして認識することができた。頭が追い付けていない部分があるが、これらを実践することで、社会にとってはよいことにつながるということを意識して、少しずつ実践でき寮にしていきたい。
w-ken
建設・土木 関連職
朝から晩まで仕事して、職場の人とご飯を食べる。これでは多様性がないという言葉にドキッとした。
kishikawa2011
人事・労務・法務
今までは個人情報の観点から在宅勤務に否定的だったが、セキュリティを強化することで、資料をデータ化しても安全という事なので、まずはセキュリティ面を確認してようと思った。
ka_endo
メーカー技術・研究・開発
基本的なことであるが、改めて学習できてよかった。
普段実施できていないことが無いかをよく考えてスケジュールの効率化をしていきたい。
h_tomoya
メーカー技術・研究・開発
在宅勤務について、効率が下がる等ネガティブな意見が実施した後では、大幅に改善されているアンケート結果は興味深かった。ただ、新入社員のようにまだ業務を理解していない層も、同様の結果になるかは気になるところである。在宅でいい業務やメンバーと、対面を重視するメンバーや業務の見極めを行い、バランスよく働き方改革を取り入れていきたい。
tani_2020
その他
業務の効率化や会議を効率化などとよく言われるが、個人のスキルに属することだと考えられがちだが、具体的にどういうことをするべきかなど、非常に示唆に富んだ内容だった。
その他のテーマも全てが具体的であり、実際の業務の現場で非常に役に立ちそうだと思いました。
terayan
メーカー技術・研究・開発
自己管理/記録の為にも、スケジューラー、弊社はアウトルックにスケジュールアシスタントがあるのでこれを拡大活用することを考えています。