
MBO(目標管理) ~目的や運用プロセスとポイントを学ぶ~
マネジメント方法論の一つであるMBO(目標管理)。上司と部下の合意の上で、業績管理と人材開発の二つを実現していくことが主な目的です。 このコースでは、MBOをより効果的に実践するために、改めてその目的と位置づけ、運用上の留意点を学びましょう。また、最近話題になっているOKRとMBOの違いについてもご紹介します。
会員限定
割引情報をチェック!
すべての動画をフルで見よう!
初回登録なら7日間無料! いつでも解約OK
いますぐ無料体験へ
あなたの仕事には、会社から課された「ノルマ」がありますか?
あるいは、数値目標ははっきり、またはぼんやりと覚えているものの、なぜその数値目標なのかはよくわかっていない…そんな方はいらっしゃらないでしょうか。
本コースでは藤田氏に、組織に課された「ノルマ」と、自らに課した「目標」の違いと、それによって人の動き方がどのように変わるのか、そしてこれからの組織と人はどうあるべきかをお話しいただきます。
変化の激しい時代にあたって部下やメンバーの自発的な働きに期待したいマネジャー・管理職の方はもちろん、副業やパラレルワークが徐々に増え、働き方のセルフマネジメントの重要性が高まる現代にあたっては、すべてのビジネスパーソン必見です。
「何が自分にとって価値ある仕事なのか」に思いを馳せながら、ぜひご覧ください。
藤田 勝利
上智大学経済学部経営学科卒業。住友商事、アクセンチュア勤務。2004年米クレアモント大学院大学P.F.ドラッカー経営大学院にて経営学修士号取得。生前のドラッカー教授およびその思想を引き継ぐ教授陣よりマネジメント論を学ぶ。卒業後、IT系企業の執行役員としてマーケティング責任者および事業開発責任者を歴任し独立。2013年PROJECT INITIATIVE株式会社を設立し、次世代経営リーダー育成、イノベーション・新事業創造分野を中心に、独自の「経営教育(Management Education)」事業を展開。ドラッカー・スクールでの学びを土台に「リベラル・アーツ(一般教養)としてのマネジメント」を実践的なリーダー教育プログラムとし、経営幹部層から大学生、高校生にまで幅広く提供。Venture Café Tokyoの戦略ディレクター、桃山学院大学ビジネスデザイン学部特任教授、ドラッカー学会理事も務める。
(肩書きは2021年12月撮影当時のもの)
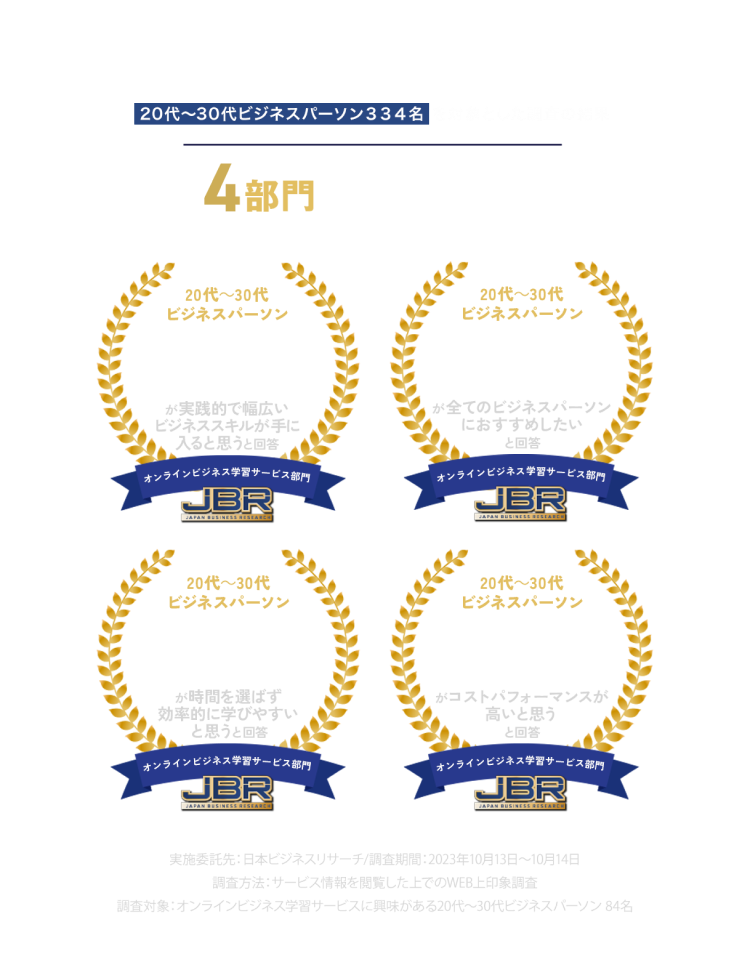
より理解を深め、他のユーザーとつながりましょう。
100+人の振り返り
katsuyuki_aka
IT・WEB・エンジニア
1.ノルマの正体とその影響
ノルマ:数値偏重型管理
シンプルな問い:なぜ頑張って仕事をする?
私には目標があります。
私にはノルマがあります。
→罠にかかったように厳しい管理を強いられている。
ノルマ
半強制的に与えられた仕事の基準量
誰にも意味がわからない数字が組織を駆け巡る
数字から上から降ってくる=異常な事態
本人が主体的に同意していない業績
利益は目的ではなく条件でる。
数字以外の情報は社員の頭に残っていない
イノベーションが起きていない
リーダーが育たない
2.ノルマに頼らないマネジメント
<コモンズ投信>
長期的な目標はない。
収益のモデル 販売で得られる手数料→一次的な販売量でない時間
お客さまは一緒に歩んで行く仲間
短期的な数字ではなく、今の行動が希望につながるのか?
バリューを実践してどれだけ長期的な価値に貢献できたか?
ノルマの代わりになるミッション
目標は無数にあるが、目的は見つからない
管理されすぎる組織ほど、本来目指している目的から遠ざかる
受け身・やらされ感
内向き化
縦割り化
プレイングマネージャー化
<未来工業株式会社>
ノルマなし。常に考える(アイディアを出す)
【事業目的=存在意義】これまで以上に問われる時代
<ノルマに頼らない組織に共通する「週間」とは?>
ノルマ数字管理をしない=放任ではない。
マネジメント原則にあった共通週間が見えてくる。
ノルマに頼らないマネジメント=組織のMission(使命)とValues(価値観)を基軸にするマネジメント
(1)ノルマに頼らない「目的」の作り方
習慣1「どこで勝負するのか」が明確
習慣2「結果」よりも「結果を生む習慣」を重視する
習慣3「数字」ではなく「顧客」「ファン」を作る
(2)ノルマに頼らない「仕事」の進め方
習慣4 コミュニケーションは「情報伝達」ではなく「意思疎通」を目的としている
習慣5 「上下関係」ではなく「信頼関係」で動いている
(3)ノルマに頼らない「人」の活かし方
習慣6 「組織の成長」の前に「人の成長」に徹底してこだわる
習慣7 マネージャーの仕事は「管理」ではなく「動機付け」である。
ミレニアル世代とZ世代 社会的意義
数字以外で「事業目的」を生き生きと語る言葉を持っているか?
「具体的すぎる」目標だけでは、人は動かない
「数字目標」は「戦略」ではない
数字を追えば追うほど、組織は「機械的になり」「冷える」
→幅広い知識が必要となる(アンテナを張る)
これからの組織と人はどうあるべきか?
「働き方」の流れ
フリーエージェント化
セルフマネジメント化
→知識労働=知識を使って成果をあげる。
自分が重要な事に取り組めている=仕事をしている
自分の仕事を自分で定義して行く。
なされるべき事を考える
→自分という資源を生かして、もっとも他者に貢献できることは何か?
monta
営業
素晴らしい内容でした!
この数値目標って名前のノルマは、仕事に対して日本のエンゲージメントを下げた最大の原因だと思う。
マネジメントにとって、数字は便利な管理ツール。
マネージャーは、数字以外で事業目的を生き生きと語れ!
moto8
その他
本の宣伝が多すぎる
mmmmmttttt
コンサルタント
目標管理、KPI管理という名称を使いながら、ノルマ管理を続けてきたということが改めて認識できました。会社、部署の目的の明確化、自分自身の仕事の目的を定義することに早速とりかかります。
a-z
営業
数字、利益が無いと会社は発展しない。
owurcbi3urhf
その他
大きな気づきと、考えるべきことがわかった。組織内でこのテーマを話し合っていきたい
ma2022
営業
・何のためにやるのか?
・何をやるのか?
・どの程度までやるのか?
実現すると誰にどのような喜びが生まれるのか?自分ができることで周囲にもっと貢献できることは何か?突き詰めて考えてもらうことで、主体性を育んでいくアプローチを増やしていきたい。
ys7710
営業
- ノルマによる管理は、唯一の正解ではない
- 自分で自分の仕事を定義・言語化すると、モチベーションが生まれる
- 数値管理は、目的にたどり着くためのマイルストーン。最終ゴールではない。
sphsph
メーカー技術・研究・開発
当人の意識の問題と感じました。
自分で実感することも、周りに伝えることも結構難しいです。
何のために・・・!
答えは自分の中にある。
rouas50
専門職
ノルマに限らず「管理」=マネジメントと誤解されている。目的を気持ちよく(いきいきと)共有できることばで示し、迷ったり上手くいかない時でもブレずに呈示できるのがマネジメントと思う。
tomoya_0528
人事・労務・法務
ノルマはじゃなくて何?と思っていたが、会社のパーパスや組織のミッション、バリューでメンバーを惹きつけ、自主的に動ける組織を作ることの重要性を理解できた。また、自分は何がしたいのか?に加えて、自分によってなされるべきことは何か?を問いに立てることは非常に共感した。
naoya0523
経営・経営企画
仕事の目的、本質は分かっていても外れてしまうことが多い。大事なことは悩んだり、決断をする時に目的に立ち戻ること。
tomohiro_883
営業
数字では目的の共有が大切であることがよくわかった。
個々人目的は異なる捉え方をしてしまうことができるので、常に目的の共有を上司部下隔たりなくできる組織でないと数字を根本から無くすのは難しいとも感じた。
djmpajmpkm
営業
目標とするかノルマとするかで気持ちの持ちようは大きく変わると感じた
8171754555
販売・サービス・事務
目標という名のノルマがついてまわる現実ではあるし、ある程度はモチベーションとしても必要に感じてしまう。
しかしMBOでも昇格審査でも、結局そこだけの評価となっていることがもどかしい。
sa5
経営・経営企画
どうやったら社員が自発的に動く仕組みにするかが組織成長のカギ
motoki-watanabe
経営・経営企画
既に我が社にはノルマから自主的な目標設定制度に変わっているが、まだ完全にノルマ主義から脱却できてない社員もいる。自身のキャリア形成のためにも目標を持って前向きに自身の仕事の意味を定義付けしてほしい。
yumirin0527
その他
ノルマは逆効果である、このメッセージを日本社会にもっと浸透させてください
いろいろなことが大きく改善されていくように思えます!
0183013
メーカー技術・研究・開発
進捗管理
tokatiobihiro
マーケティング
ノルマはなんとなく押しつけられている
感じ。
ビジョンなど明確にして取り組む
ftec
メーカー技術・研究・開発
ノルマの数字を追うことが多く、MVVに紐づかないこともあると思った。短期的ノルマや目標の達成のためでなく中長期的ビジョンのために仕事をしたい。ノルマ重視の会社は必達の風土があり、目標達成のための仕事・コンプラを軽視すると不正などが発生しやすい。目標の数字の根拠も対前年の成長が掲げられているが、具体性が薄く部門や部署、下手したら担当者に手段は丸投げであったりする。その上で提案も通りにくいことがあると、組織として離職などが発生しやすくなる。数字を追うだけの烏合の衆になってしまう。
MVVを重視するなら採用や新人研修の段階から、MVVの浸透をはかり組織を運営しないとならないと思った。
t_i_z
メーカー技術・研究・開発
組織の数値目標が実質的にノルマ化しているという点に共感しました。
現在の組織では中長期的な目標やビジョンが共有されてはいるものの、短期的な数字の方が重要視されていると感じる。
その理由は、短期的な目標数値が高すぎることであると思われる。組織として目標を達成するためにも、まずは達成できる基盤造りが重要だと感じました。
fu__
販売・サービス・事務
利益は目的ではなく条件である
数字以外で「事業目的」をイキイキと語る
セルフマネジメント
現在の自分には出来ていない事。なので
小さな事から行動していく!
残業なし/ノルマなしの未来工業の「常に考える」にとても興味がある
japanet
専門職
MBO確かに数値管理している
上位の目標に対して何をするのか自分で目標を決める
そのタイトルが目標値
数字を入れないとよく却下されていた。
今の仕事は数値で管理していないが主体的に目標を達成するために自主的に機能していない。
指示待ちを希望するメンバーもいるが指示が多いと不満も言う。若いからなのか・・・
sastoshi1229
営業
数値目標ばかりを追われるうちに、しんどくなっていた。数値目標も会社の経営上、必要だが、「自分によってなされるべきことは何か」という一言が、非常に印象に残った。
kp
経営・経営企画
営業の進捗管理がままならない自社の現状においてはあえて厳しい監視下の基、定例会議等で「お目付け役」的な立ち位置で進捗管理が必要であると感じている。
本動画のテーマにある「ノルマは逆効果」に関して理想論としては賛成しつつも、会社を成長させたり繁栄させる為には自律性・当事者意識を醸成させる一歩手前の達成力・やりきる力を養う必要がある。
会社の置かれた状況・ステージ別で定義は変わってくると感じ、一概には賛成しえない内容であった。
horiken55
メーカー技術・研究・開発
目標を数値だけでなく、それぞれの、また組織、社会としてのありたい姿を共有しあうことで、メンバーそれぞれのセルフマネジメント力を上げられるのではないかと感じた
petsu
営業
生きた目標を設定し落とし込めるかどうかがとても大切だと思いました。
toshi21
営業
数字はあくまでも便利な管理ツール。そこに固執するリーダーでは駄目だということ、うちの会社でも当てはまります。
hiro4725
資材・購買・物流
『ノルマ=数字』といく考えこそナンセンス。正しいビジョンや戦略であれば、数字なんておのずと付いてくる。その中で自分のプラスαをいかに発揮できるかだと思う。ノルマという考え方自体あり得ない。出すべき結果。
yashimay
メーカー技術・研究・開発
今の私にはノルマを作らない経営をするのは、勇気が必要です。
勇気を出して何をするべきかを考えます。
morimotoa
営業
短期の利益か、長期の利益か。当社で言うフローとストック。の意識をする。
数値のみによる管理はNGと理解したが、数値の管理も必要であると考える。
mote_san
営業
ノルマに頼らないマネジメントをするとしても結局組織を運営する以上、業績管理が成果に結びつく事になるのでマネジメント層は二つの軸で行動する必要があるという事か
yasushi0102
金融・不動産 関連職
日常業務において実践する
s-hamamoto
営業
部下の管理をしていく上で、ノルマ(受注)だけでなく自分の仕事・役割を共に定義し納得した上で、進めることが重要と思う。
toku-ken
営業
基本的には自分の気の持ちようだと思う。ノルマと感じるか、目的に向かうための目標ととらえるか。
目的を持って自身の存在意義を持ってもらえる様、メンバーに伝えていきたい。
fujim
営業
数字での管理や膨大なKPIに追われ続ける生活に疑問を持ち、試聴しました。
【何のためにレンガを積んでいるのか】
自分の仕事について、改めて考え直すきっかけになりました。
1337ibuki
専門職
数字はノルマとまではいかないにしても指標の一つとして掲げている。個人差が顕著に出て統制が取れなくなる恐れもあり、客観的に評価できるものであるため外すことはできない。
自分は何をやりたいかを明確にして、それを自分の言葉で語る。これは、自己管理の原点であることを常に考えながら職場管理をする。
に
m-masuoka
営業
正に数字管理、目標数字を常に追っている状況であり、目的を真に語っていなかったと反省する。
周りを含め、周りを巻き込み、その意図をしっかり伝え得ていきたい。
116178
メーカー技術・研究・開発
目先の数字より、考えるベースが大事ではと感じました。改めて自分の存在意義は何か、立ち代って考えたいと思いました。
ftomo
人事・労務・法務
数字を追わないという会社のビジョンの中で、成果が出ない状況に陥り、全社的に(特に役員)焦りが出始めている。やろうとしていることは正しいと、この動画でも自信が持てたが、やり方で迷走している。ノルマを考える中で、少し変化を起こせそうな気がする。
a95091
営業
目標の意味を語る
n-k0925
金融・不動産 関連職
今までノルマについて、深く考えていませんでした。
「やらなければならないもの」や「当たり前に存在するもの」という考えでした。ノルマがなくなればどれだけストレスが軽減できるのかと日々考えてしまいます。
自ら考え行動し、会社・社会に貢献する。また、自分の生活を豊かにするという働き方は主体性が求められ、必ずしも全ての人ができる働き方でないと考えます。
組織にとってノルマはは永遠の課題だと思います。働いているので全ての人がやりがいを持って働けるように考えていきたいと思いました。
suzuki_n365
メーカー技術・研究・開発
ノルマという言葉で表現されていなくても、数値に縛られているケースは多々あります。特に厄介なのは、その数値について誰も意義をこたえられないという類のもので、これは実感としてモチベーションは下がることが多いです。
"自分が重要なことに取り組めている"という感覚を得る事、これが自身にとっても、メンバーにとっても組織成長の上で重要になるキーファクターだと感じました。
01372
営業
お仲間やファンを作るというキーワードは新鮮でした。仲間とはwin-winの関係であるべきだと思う。
maru_masa
営業
「ノルマは逆効果 なぜ、あの組織のメンバーは自ら動けるのか」を受講した。
ノルマはその語源から半強制的に与えられた時間的強制も付加された労働量と定義されるとのこと。ノルマに頼った短絡的な評価の管理を行えば長期的な目標の達成は難しいことを学んだ。その理由としてノルマ至上主義はメンバーが受け身、内向き、縦割りの陥りやすいとのこと。
ノルマに頼らない目的の作り方として、会社(自身)のどの強みで勝負するか、結果よりも結果を生み出す習慣に重点を置くこと、、また数字よりも顧客・ファンを作ることが長期的な目標の達成を目指せ且つ短期的な結果も生み出す近道だということを学びました。
soccergoal
営業
セルフマネジメントによるポジティブなノルマ設定にトライしてみたい
mana202006
その他
目的意識をもって,業務に取組みたい。
shusuke-yamada
その他
ノルマを課す理由としては、管理がしやすいという利点があるからです。
完全に同意したとは言えない理由としては、会社内での上下関係があるからです。
数値が上から降ってくることが異常であると気が付かないような形にしているところが恐ろしいところです。
他者のせいにできるから、目が死んでいくと考えられます。
murami
営業
私は営業職ですが、とても気持ちが救われた内容でした!
管理すれば管理するほど創造的な人材は育たない、というのはまさにその通りだと思います。
イノベーションを起こすのは、人によって管理されるのではなく、セルフマネジメントをしていくことが重要。私自身「やらされ感」がでた時点で、途端に思考ができなくなるので、自律してセルフマネジメントを強化していきたいです。
saepom
営業
例えば「自社の製品を売る」を目的にするのではなく、「自社の製品で顧客の問題解決に貢献する」「製品の良さをうまく伝えて解決策に気づいてもらう」と置き換えて取り組んでみる。
tomoaki_matsuda
営業
未だに数値での管理しかされておらず部下も嫌気がさしている。目標の定義を行い意識付けしていきたいと思います。
j_nakamura
経理・財務
ノルマの異常性に気づくことなく、社会人生活を送るところでした。ありがとうこざいました。
osaka-love
コンサルタント
ノルマは過去の遺物ですか??
yanada1228
その他
自分の仕事を、目標数値ではなく、どんな課題を解決するか、で語れるようにする
yuchikochi
営業
ノルマというものには私も違和感を感じることが多かった。無理な業績であればなおさらだ。
いかにモノを作るかが大事であった戦後~高度経済成長期であればノルマという考え方がはまったと思うが、
世の中がより高度化、複雑化した現代において、単純に数字目標を追って業務をするのでは、
確かに日々の納得感がうまれてこないと思う。
私は数字は後からついてくるものと割り切って、メンバーに対して真の目的を問いながら、日々の動機付けをやっていきたいと思う。
liner2323
コンサルタント
ドラッカーの言葉の中で、「なされるべきことを考えることが成功の秘訣である。何をしたいかではないことに留意してほしい。」が紹介されていましたが、とても深いと思いました。何をしたいかと考えてしまいがちですが、なされるべきことを考えるようにしたいと思います。
masa49
経営・経営企画
自分という資源を使って他者にどんな貢献ができるのか、この言葉を探してました
tsuufy
その他
主体的に自分が、自分たちが何を行えるか、社会に対してどの様な貢献が出来るのか、プロセス立てて考えていく事が重要である。
yuji_xxx
販売・サービス・事務
20年程前に新入社員として入社した頃は、ある程度の裁量を与えられ楽しく仕事をしていた記憶があります。最近は数字ばかりが強調され、ルールでがんじがらめにされている感覚が強く、毎日が苦痛に感じてしまいます。
ishiiyusuke
販売・サービス・事務
数値目標の考え方を教育する際に使える。
tetsuya_0829
経営・経営企画
このようにself-controlができる人材が多ければ、managementは楽ですね。
実際には、能力の異なる人達の集合体が会社・組織であるため、それを如何に動かすかのが難しい。能力が低い人でも、少しでもself-controlさせ、前向きに仕事をさせることができるといいです。
また、大手の営利企業であれば、数値目標があること自体は仕方がない。株主というより投資家からの圧力が強いため、経営者はその要求に何とか応えようと短期・中長期の収益・利益目標を定める。その目標を何等かの方法で部門に割り振り・部に割り振り、最後は個人の数値目標となる。
このカスケードダウンの仕組みを説明しない経営者もしくは理解しないmanagementがいると、社員個人個人の数値目標が意味をなさなくなり、やる気がそがれる。上記二つを改善し、キチンと説明すれば、社員の数値目標に対する理解は格段と上がるはず。(といっても、達成が困難な数値の場合もありますが。。)
narumichan
経営・経営企画
期間毎の数字、ノルマを全くなくして、目的に向かうことは、全ての社員が行うことは難しいかとは思う。ただ、自分に何ができるのか、もくては何かを確認しながら動くことは大切だと思う。
自分の会社が、顧客や地元や同業者や社会にとって「価値ある会社」に、自分が働きがいがある、人が入りたくなる、家族に自慢できる「価値ある会社」を目指して、明るく厳しく前向きに頑張っていきたい
keinona
専門職
ノルマ(数値目標)があることで、本来達成すべき目的(例:顧客への貢献、など)を意識しなくなってしまう、という点はその通りだと思う。一方で、売上ではなく顧客への貢献度で評価する、としても、結局は「貢献度」を客観的、公平に測るためには何らかの数値が必要になると感じる。成功した会社で具体的にどのような指標で業績評価をしているのか知りたい。
sakikawa
営業
自分自身にも、部下にも非常に有益な内容だと思いました。共有して、自分、部下の成長につなげたいと思います。
osengi
経営・経営企画
ノルマで人を縛るつもりはないけれど・・・
仲間意識で共に組織を支えてゆこう!と
皆が思える組織は理想ですね。
chi-kun03209
販売・サービス・事務
セルフマネジメントという言葉が自身の存在意義をいかに目的を持ってメンバーに伝えて行くという事を考えるきっかけになりました。
isobeshinji
経営・経営企画
数字で管理したり、確認することが多かったが、数字以外の言葉で事業計画をイキイギと部員に語ることを心掛けたい。またあまり具体的な目標や数字を追うような管理はやめ、個々の中長期的な成長を意識した指導を行いたい。
ichikawas
営業
営業職で数値に追われることがありますが、自分の仕事の定義を自分の言葉であらためて考えたいと思いました。
aki1224
マーケティング
知識労働者としての自覚を再認識しました。
takeshi-toyama
営業
数字以外の目的、仕事の意義を伝えていき続けていこうと思います。
moonmasa
資材・購買・物流
きちっとした戦略を立て、原理原則に反しないやり方、道理にあっているやり方をすることで結果はついてくる、結果を出せる、そんなマネジメントを目指したいと思います。
kk12645
メーカー技術・研究・開発
ノルマにならない「目的」を作る。何のためにその業務をやっているのか。というのを感じて日々取り組んでいきたい。
tatake
IT・WEB・エンジニア
ノルマについて聞いていくうちに自分の会社が時代に逆行して数字化というノルマを課しているように思えた
henkuri
営業
自分の仕事を定義する。トライしてみます!
kamikawa75
営業
ノルマ達成は目的ではなく、手段と置き換える
または今の自分の仕事の定義を今一度考えたいなと感じました
ozawa_h
IT・WEB・エンジニア
「ノルマ」の語源がロシア語で組織が強制的に割り当てた労働の目標量であることを知りました。
MBOは「目標による管理」は本来は「management by objectives and self-control」であり「目的・目標の共有と、自己規律によるマネジメント」であることも知りました。やはり元になるドラッカー「The Practice of Management」を読むべきだと実感しました。
im5462
メーカー技術・研究・開発
リーダーシップを発揮する立場として、メンバーの力を引き出す上で、重要な示唆をもらいました。
kuwa7683
経営・経営企画
数字やノルマを廃止。といいながら隠れノルマあり。結局、みんな数字を意識してしまう。短期的な目標に縛られず、中長期的な目線で言われるが、その中長期的な成果をきちんと評価する仕組みがなければ機能しない。結局、短期的な業績をベースに賞与などで差配するのは矛盾している。
honest
営業
自分の仕事を自分で定義する。当たり前のようですぐ答えられなかったので、衝撃だった。ノルマは当たり前となっていたので、意識転換に良いテーマだった。
ikuta_yuusuke
資材・購買・物流
具体的すぎる目標では人は動かない、という点について、自ら考える機会を奪わないよう、
考えさせることで自発的に動ける形に変えていきたい。
styt
経営・経営企画
とてもダメになりました。数字だけでは人は動かない。なるほどです。
malan_25
営業
業務で活用するには、自分によってなされることを具体的にイメージし、使命感を持ってやり切ることが大切だと考える。そうすることによって成功体験を積み重ね、働く意味や目的を見出すことができるだろう。
kuwashima-t
営業
組織マネジメントを考えた際、成果を最大化し持続的に達成することが求められるマネジメントにおいて、ノルマではなく目的をしっかりと捉え中長期的に仕事を捉えることが良いと感じた
fjjman
IT・WEB・エンジニア
業績を上げるために、利益は目的ではなく、条件であることを理解して、メンバーのマネジメントやコミニケーションに役立てたい。またメンバーには何をしてほしいか、何をしたいかだけでなくでなく、自分という資源をつかって、もっとも他者に貢献できるものは何かを考えてもらって、苦しまないやりがいともった仕事をしてほしい。
kato_hiroyuki
経営・経営企画
MBOの本当の意味やセルフマネジメント出来る知識労働者でなければならない事に感銘を受けました。
chro_hiro
専門職
X理論とY理論として考えるとノルマはX理論であり自発性を阻害する要因になる。人が動くのは内発的な動機付けであり、動機付けをするためには企業理念へ共感できるかであろう。
shima123
IT・WEB・エンジニア
やりたいことではなく、なされるべきことは何かという観点で考える。
数値目標ではなく、どのような価値を創るかが大事。
saoki_
金融・不動産 関連職
ノルマは、主体的に設定した目標ではないもの。印象的です。
capitalist_pig
クリエイティブ
結局、仕事でもなんでも、正しいゴールを決めてそこに向かって走らないと、いい結果は出せないですね。本来、そこに全力を尽くすべきなのですが、目標を作る管理職や経営陣がラクをすると、簡単に決められる数値目標に走ってしまいがちだと思います。また、数値目標で結果を出して出世した上司は、部下にやはり数値目標を押し付けてしまいがちです。
sknesh
金融・不動産 関連職
「ノルマによる管理」が時代遅れになる、というのはその通りだと思います。一方で、各自がそれぞれ、自分自身の目標=ノルマを作り、それに向かって進んでいく、という考え方もあるのでは、と考えさせられる講義でした。トレードオフの考え方ではないですが、フリーライダー問題が生じるのでは、と疑問もあります。
ryorthia
その他
自分自身で設定したものや、同意があればノルマではない。
数字ではなく、定性的なものはノルマに見えないが、実はそれが1番きつい。
shunma
メーカー技術・研究・開発
数値目標は大切だが、それだけでは人は動かないことがわかった
shikatabanna
営業
本人が納得できる目標を設定することが必要ですね。
kasuyaharuki
メーカー技術・研究・開発
とてもためになりました。
gon40
マーケティング
自分自身にとっても、関わりのある仲間にとっても、一つ一つの仕事や、働くことについて、長期的な視点で考えたり、話し合ったりできれば良いと思いました
tsuryu
金融・不動産 関連職
数字では目的の共有が大切であることがよくわかりました。
個々人目的は異なる捉え方をしてしまうことができるので、常に目的の共有を上司部下隔たりなくできる組織でないと数字を根本から無くすのは難しいとも感じました。
tatsuro-kochi
メーカー技術・研究・開発
数字以外で目的を語る言葉はあるか? 当面のニーズと長期のニーズを調和させなければならない 何のために私たちはいるのか、使命、ミッションに立ち返る これらを意識していく。バランスが大切だと感じた。
saitou-shin
その他
現在の管轄部署の役割、会社及び取引先から何を期待されているのか改めて考える機会になりました。部下に対しても、日々の作業に没頭させないように、各自が自分自身をセルフマネジメントする気持ちになるように、本日の内容を踏まえ、的確に伝えていきたいと思いました。
sarend6-
営業
会議の場で売上 利益の進捗報告やリカバリー策の議論が主流になりかけていたがそれとは違う目標設定と共有を主流とすることにシフトチェンジします。