
Marketing of Life
将来「やってみたいこと」や「なりたい姿」はありますか? では、それをどのように叶えるかの具体的な“戦略”は立てているでしょうか?なかなか難しいですよね。 実は、マーケティングの考え方を、個人のキャリア戦略のアプローチに使うことができるんです。本コースでは、マーケティングミックス(4P)やパワーと影響力のおさらいをしながら、キャリア戦略への応用の仕方を考えます。4Pやポジショニングの考え方を用いて、“自分自身のマーケティング戦略”を立ててみませんか?
会員限定
割引情報をチェック!
すべての動画をフルで見よう!
初回登録なら7日間無料! いつでも解約OK
いますぐ無料体験へ
・イノベーションに関心のある方
・プロダクト、ビジネスの企画に携わっている、または関心のある方
物が溢れる時代である現代において、イノベーションを起こす難易度は高まっているとも言われます。しかし、これからの時代は「意味」のイノベーションを起こすことで新しいビジョンを提供できるという考えもあります。
「意味のイノベーション」という言葉はイタリア・ミラノ工科大学のロベルト・ベルガンティ教授が著した「デザイン・ドリブン・イノベーション」に登場する言葉で、極端な言い方をすれば、製品の仕様やパッケージをまったく変えることなくイノベーションを起こす方法と言われています。
このコースでは、「デザインの次に来るもの」の著者であり、ロベルト・ベルガンティ著「突破するデザイン」の監訳者でもある安西洋之氏に「意味のイノベーション」をテーマに語っていただきます。
「電気がある時代に、ヨーロッパではなぜロウソクが売れ続けるのか?」
この問いに対する答えが気になる方は、ぜひこのコースをご覧ください。
安西 洋之 モバイルクルーズ株式会社 代表取締役
いすゞ自動車に勤務後、1990年よりミラノと東京を拠点としたビジネスプランナー。多くのデザインプロジェクトに参画。また、異文化理解アプローチ「ローカリゼーションマップ」を考案し、執筆や講演等の活動を行う。著書に『デザインの次に来るもの』『世界の伸びる中小・ベンチャー企業は何を考えているのか?』『ヨーロッパの目 日本の目 文化のリアリティを読み解く』、共著に『「マルちゃん」はなぜメキシコの国民食になったのか? 世界で売れる商品の異文化対応力』。「突破するデザイン」(ロベルト・ベルガンティ著)の日本語版監訳・解説。
(肩書きは2018年6月撮影当時のもの)
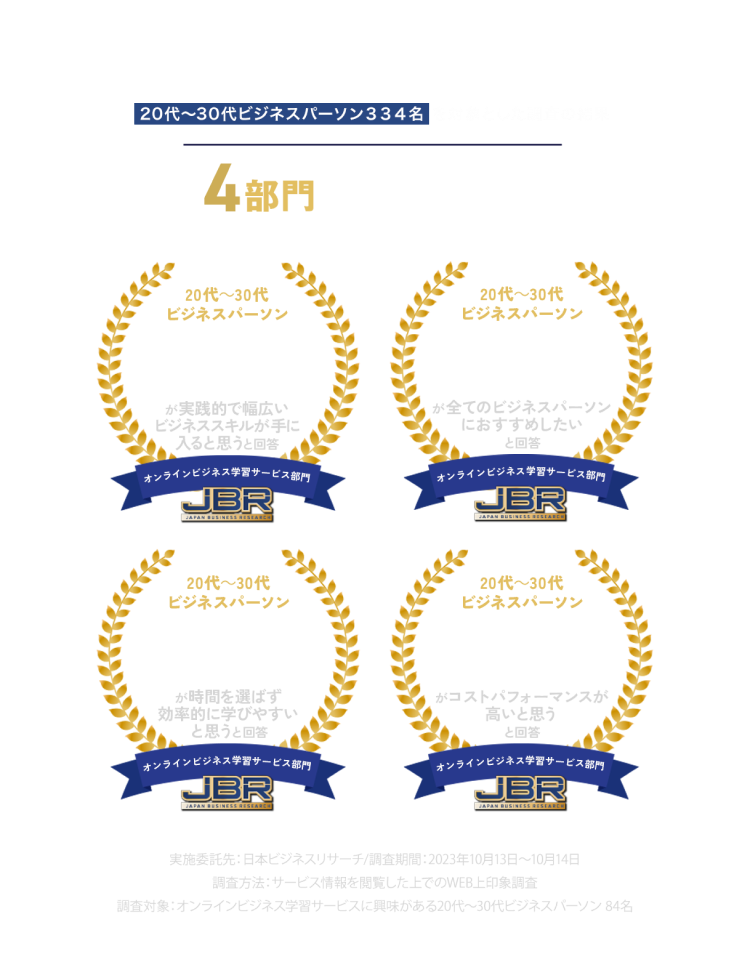
より理解を深め、他のユーザーとつながりましょう。
100+人の振り返り
teruo_2000
マーケティング
何を言いたいのかよくわかりませんでした。
k-m-2
経営・経営企画
ビジネスにおける意味のイノベーションとは、コモディティ化しやすい問題解決型ではなく、モノの意味を再定義し、新しい価値をもたらすこと。
例として挙げられている企業は、ユーザー中心のデザインでも、外見のデザインでもなく、「意味」をデザインすることで成功を収めている。
また、必ずしもテクノロジー依存型ではないイノベーションということで、様々な可能性を見出すことができるポジティブな内容だと思う。
k_k_k_k
経理・財務
終始何を伝えたいのかが分かりませんでした。
ろうそくは技術的には不要であるが、いやしを求めてある程度の市場規模があるとのことでしたが、それがイノベーションと何の関係があるのか?と疑問です。海外では停電も良く起こると聞くので、単純に市場のニーズがあったからでは?としか思えませんでした。。
商品にストーリー性を持たせて、それをアピールしていくという意味合いでしょうか?
kayoko2020
その他
・「意味のイノベーション」。ベルガンティ2009年。同じプロダクトに別の意味を持たせる、これまでとは異なる文脈におくことで、新しい価値、ビジョンを提供すること。
・プロセス。一人で考えまず動き出す→スパーリングパートナーと批判的な対話→ラディカルサークル→ビジョン、コンセプトができたところで解釈者に問いかけ→ユーザーに意見を聞く
・1人ワークが重要。人間洞察に置いて深く掘る。多角的なものの見方をすることを習慣づける。
・デザインシンキングは外→内。市場でユーザーの声を聴く。意味のイノベーションは内→外。
・0から1でなくていい。歴史に埋もれたものに価値を見出し活用する。
⇒差別化戦略に重要な視点だと思った。
jirushi29
営業
意味のイノベーションとは、コト・モノに対して、ターゲットが共感する意味を吹き込むこと。と理解する。
営業という仕事に置き換えたときに、顧客への提案内容に顧客のビジョンと重なる意味を吹き込むことによって、その提案は何倍の価値になる。
プロフェッショナルはこの作業を意識的であれ、無意識的であれ実践している。
顧客に向かう先を示し、その向かう先の行き着く意味を共有できる営業を育てたい。
ho73
マーケティング
「意味のイノベーション」というタイトルは納得感がありましたが、内容はよくわかりませんでした。
ot-take
メーカー技術・研究・開発
価値を付加する定義付けることの大切さを理解した。
ヨーロッパは圧政から自由を勝ち取った背景から文化や美しさを大切にしており、価値を定義し直すという俎上があると思う。
その凄さは、常に先駆者を走り市場の価値を保ち、追いつかれれば定義を変えてやり過ごし、旧定義の価値は汎用化してからしれっと使う所にあると思う。
例えば車産業である。
不利になれば、二酸化炭素の定義付けでクリーンディーゼルで、SDGsの定義付けで電気自動車で、今度は水素でやり過ごそうとしている。
今ヨーロッパに技術がなくても定義を作れば日米中が技術を作り、また不利になれば定義を変えてやり過ごしつつ旧定義で汎用化した技術も使っている。
技術を作れば市場の先駆者でいられると思っていたが、
定義を作れば同じく市場の先駆者で常にいられるのは凄いと思う。
ta-tsu-ro
IT・WEB・エンジニア
私はエンジニアだが、その為なのか「開発に依存しないイノベーティブ」という考え方が非常に新鮮に思えた。
日常業務では、お客様・協力会社の皆様に、技術的な意味や、今起きている問題の意味について、説明や問題提起をすることはあるが、今行っている開発がお客様にとってどんな意味があるのか、社会的にどんな意味があるのか、この開発がお客様の将来にとって今後どんな意味を持ち得るのか、そういった視点からの「提案」が行えていないと考えました。
「意味のイノベーティブ」
まずは業務の「そもそもの意味」について考え直し、今までとは違った?今まで以上の?イノベーティブを職場で巻き起こしていきます。
kameco
販売・サービス・事務
「電気のある時代になぜロウソクが売れるか」は確かにそうだと思った。私たちは新しいものにドドッと流れるが、落ち着いてくると「好きなもの」「きれいだと思うもの」に戻るというか、気づく。その時に新しい意味が提供されていると、求めている人には見出すことができるのだと分かった。
oniryu
資材・購買・物流
日本で起業するにおいて、意味のイノベーションを考えることは大事だと感じた。新しいものをクリエイトするのも良いが、過去のものにも今風に流用できるものもあるので、自分の盲点に気づかされました。
test_
メーカー技術・研究・開発
個々人がcoolと感じるものを重要視するというような印象を受けました。
不毛な性能競争や全部入りケータイなど価値観が比較的画一的な日本人にとっては確かに苦手な分野なのかもしれない。
tommy_ito
マーケティング
意味のイノベーションの話は分かったのだが、何が一番言いたいのか、疑問でした。
dictimboy
建設・土木 関連職
周りの意見ばかり気にして、自分の考え、意見を深堀りしないまま、ただ何となく組織の一員になっているようでは少なくとも自分がイノベーションを起こすことはないだろう。まずは自分から何か意見を持てるよう努力が必要だ。
yuki_hiro
人事・労務・法務
意味のイノベーションとは、「いいな」という想いへの共感と捉えました。
markunn_2013
金融・不動産 関連職
抽象化と具体化の往復運動というより抽象化の一方通行的講義でしたね
884
マーケティング
既存商品にこれまでと違った価値を見出して売り出していくことの重要性を理解しました。
th0588
その他
何か難しくて理解できなかった。
asai_mt
メーカー技術・研究・開発
編集のせいかな、説明が非常にわかりづらい。
ある程度知っていること前提の内容説明になっていて初見の人にはかなり厳しい動画になっている気がする。
tasaka0514
マーケティング
普段からヨーロッパ人と仕事をする機会が多いが、新しいアイディアを製品コンセプトまで持っていくアプローチにおいて、個からペア、サークル、社外の専門家、ユーザーというステップを踏んでおり、まさに「デザインドリブンイノベーション」を体現していると感じた。
ishii201
営業
一人で深く考える、ペア(反対意見を入れて)でディスカッションする、複数でコンセプトに精通したテストをする、ユーザー、市場関係者でのテストをする。
実証実験におけるデザインコンセプトを明確にすることで、戦略の軸を明確にしていく。(やるべき順番が異なりので注意)
harunosuke
その他
モノではなく、意味におけるイノベーションという切り口で物事を考える視点を持ちます。
saito-yoshitaka
メーカー技術・研究・開発
一人で深く考える事が重要であり、全ての基本となる事を学ぶことができました。
hiro_yoshioka
メーカー技術・研究・開発
なるほど製品性能が高いだけが価値ではない。
そういうこともあるのですね。
あたらしい価値(意味)をみつける それがイノベーション
wkiymbk
IT・WEB・エンジニア
ライトなインタビュー番組風の内容で、”意味のイノベーション”、”デザインドリブン・イノベーション”という言葉の持つ雰囲気を掴むに役立ちました。その知識は顧客との会話、職場での雑談・ブレストで活用します。
hiro_0505
メーカー技術・研究・開発
一人で考える。当たり前ではないものを生み出すうえでは、やはり重要なんだと感じた。審美眼を鍛えることは人固有が持つ感性であると同時に、生物として安心できるものは、必ず愛される要素を持てるのかもしれない。先ずは、自分の感覚を声にすることを実践していきたい。
14001
資材・購買・物流
今もラジオとかが生き残っているのも意味のイノベーションの一例だと思いました。又、一人で物事を考える事は自分なりの意見や見解を持つ上で重要になると思いました。
tan_tan_
クリエイティブ
意味のイノベーションは既に存在している物事の捉える側面を変えたり、解釈を与えたり、使用方法を変えたりすることで、新たな命を吹き込むイノベーションなので一見すると誰にでもできることのようだが、実際は常識や固定概念を一旦取っ払ってリシンキングするという難易度の高い手法だと感じた。
k_uru
経理・財務
活用が難しいですが、モレスキンの事例を転用できるケースを常に考えたいと思います。
g_y_s_
マーケティング
これまで生み出された製品も、時代や状況によって、違った使い方や意味合いを変えることにより、イノベーションに近い効果が得られる場合があることが判りました。
kei-3
メディカル 関連職
業務で活用するには、何事においても、先ずは1人で考える習慣をつけることが大切
294041
IT・WEB・エンジニア
意味のイノベーション、初めての言葉でしたが、昔からあった手法のように思いました。「意味のイノベーション」そのものが、意味のイノベーションだと思います。
考え方を変えることでもう一度命を吹き込むことが出来ることがわかりました。
csl_kojima
IT・WEB・エンジニア
理解が深まりました。
tikk_kkit
経営・経営企画
・意味のイノーべションは、
製品自体を変えずにそこに新たな意味、価値を創造すること。
コストもかからず日本企業でもできるとのことだが、
多く生まれていないのは後半で話している「一人で/自分で考え、意見を言う重要性」によるもの、繋がっているのか?。
日本では、教育段階から周りに合わせることをよしとされてきているので、これまでと違う視点での異見/意見を出せる人は多くはなさそう。
考え、意見を言うにはまずは一般教養、一般的な意見といったベース身に付けることが重要かと思った。
manamana-202207
金融・不動産 関連職
最後の一人で考えて発信するというのは共感できまして。
hk09
営業
今あるモノに対して、これまで考えられていなかったような新しい角度から、再度利用価値を検討する。まずは一人でとことん考え、発信する。
kuma_2
その他
私⇒ペア⇒グループ⇒解釈者
大事にしたい。
一人で考えることを大事にすることは、いいことだ…と、肯定され、前向きに生きられる気持ちがしました。ありがとうございます。
yoshi_777
営業
面白かった
snufkin14
販売・サービス・事務
既存のモノから新しい価値を生み出すことは、時代の流れをうまく読まないと難しいと感じた。
デジタル化が進むと、アナログの温かみみたいなことが取りざたされる風潮があるが、そこは一つのきっかけだろうか。
masuchan
営業
深みのある意味を作るには日常生活の中で多角的な視点で物事を深く掘り下げていく癖を付けて行くことが大切と思いました。
toshikoizumi
販売・サービス・事務
確かに、サービスを作る上で、問題解決になる事が強調(正しいのですが)されていて、意味のイノベーションにまで意識が回ってなかったと思いました。レコードとか、フィルムカメラなども癒やし、ゆとり、柔らかさなどで再注目されたと思います。アップデートして埋もれているものをサルベージする意識も必要だなと感じた。
cobra2020
マーケティング
人の意見を聞く前に自分一人の考えを整理しておくことは最重要。また自分の考えたこと、感じたことを人に話すことは考えを整理する上で重要。そんな基本的な事や、物に人が意味を与えることが出来ること、歴史からそのものの持つ意味を再発見し価値を高めることが出来る事など「意味のイノベーション」結構深い話だった。
ichi_t
経営・経営企画
講義そものもへの感想ではありませんが、他の視聴者の振り返りを眺めて、何を言いたいのか分からない という軸の振り返り方が、日本ぽいと思いました。
eizan_1000
IT・WEB・エンジニア
意味を問い直して新しい価値を見つけてゆきたい。
user-2018
IT・WEB・エンジニア
デザイン思考を研修やビデオで学んだあとでこれを見たので、
デザイン思考にやや批判的な感じがあり、少々戸惑った。
(デザイン思考が0⇒1的発想に対し、意味のイノベーションが既にある価値を活用する、という点)
ただ、研修や業務でのグループワークやブレインストーミングにおいて、
1人ワークなしでいきなり始めるケースが多く、疑問を持っていたので
どんなプロセスにおいても一人でまず考えることが重要である、というのは共感できた。
kotetsunonaka
専門職
スパーリング相手と意見交換して訓練するところは共感します。
mitch7405
マーケティング
意味のイノベーション 1人で深く考える重要性 既知の事、物にもう一度意識してみること。なるほど
hide0303
マーケティング
少し難しかったですが、まずは一人で考えるを実践していきたいと思いました。
2020hiro
メーカー技術・研究・開発
web,SNS等の多くの情報に溢れる時代,ひとりで,身の回りの現象,事体を解釈して,考えることは,重要で,新しいものを作りだけでなく,過去にあるものを歴史的文脈から離れた解釈を行い,ひとりから発したイノベーションのアイデアを,少しずつ自分から回りへ広げて行き,社会で受け入れられるイノーべーションと一致するか慎重に探索しながらイノベーションを起こすという意味のイノベーションは,非常に勉強になりました。
s_narusue
メーカー技術・研究・開発
あらゆる価値は既にある前提で、意味のイノベーションを起こし、活用のすべをひねりだす考え方はとても魅力的である。
大きな費用もかからず一人ワークでできることから新しいビジネス創出する際には必ず実施したい。
koji0419
経営・経営企画
海外との思考の差異等参考になった。歴史に学ぶことも重要であり、これは実践してみたい
gozags
経営・経営企画
一人で深く考えてみるということは、ある意味当然であると感じたが、その一方で、日々の業務の中で忙しさに翻弄されることも多い中、その当然の一人で考えるという過程を踏んでいないことが散見されると反省した。
suusan
IT・WEB・エンジニア
既存のものについても視点を変える、方向性を変えてあげることで新たな価値創出につながることを実感。判断力、思考力を養いながら自分で発信することが大切。
kamiishida
営業
停滞するサービス既存製品の立て直しに活用
yamamoto-y
マーケティング
想像力
kodama_1967
営業
埋もれていそうな価値を探してみようと思いました。
tf317
その他
ものについて、改めてそこにある意味、価値を問い直すとともに、それぞれの意味、価値については個人毎の好み、希望を尊重することが重要な時期が到来している。
jagge
建設・土木 関連職
一人で考えるためには、まず一人になる時間の確保が必要で、これを1日10分でも毎日確保する事が重要と考えます。まずは時間を確保してその時間を有効に活用致します。
misaking
マーケティング
独りで考える。
大切なことだと思う。
MOTHER houseの山口社長が講演で仰っていた。
毎朝散歩しなが独りで考える時間を持つ。
良いアイデアだと感じたら、それが視覚化されるまで考え抜く。
ありったけの選択肢を挙げてみる。
考えることをルーチン化せねば、定着しないのだ、と感じた。
nakasan
メーカー技術・研究・開発
すでにあるはずの価値を上手く引き出すことができる欧州と0,1で価値を創発する米国。安易な比較だが文化の歴史が関係しているかも。文化の歴史であれば、日本はどうか?本来は欧州のような考え方もできるはずだが。普段の生活の中からいろいろなことに興味関心を持つことから意識的に始めてみようと感じた。
kfujimu_0630
マーケティング
非常に興味深い内容でした。終戦後から続く日本企業の改善モデル、0→1モデルを現在も踏襲した事業を展開している日本企業は多いですが、もう通用しないのではと危機感を持ちました。1人で考えることの大切さ、言い換えると、アンテナを張って常に考えているか?が問われていると個人的には思います。考えることは、すぐに1人で始められることなのでこれから実践します。
gmd
営業
意味のイノベーションというのは非常に心に刺さる言葉だった。
既存の価値を改めて見直すという事は、新しい価値創造への切り口になると思う。
何も新しいものが全て優れているのではない。SDGsが唱えられる昨今では、特にその思いを強くしている。
t-masa
営業
その製品の本質、付加価値、本当の意味を考える必要性を痛感致しました。
silver0809
営業
月並みだが、Appleは電話に「通話」以外の新たな意味を定義して成功したし、航空会社がコロナ禍において人財に「航空事業」を超える意味(例えば「人を幸せにする」のような)を定義してトライしているとも言える(もちろん雇用を維持する側面が強いが)のではないかと思った。
masr31
IT・WEB・エンジニア
難しかったのですが
意味のイノベーションは従来の問題解決型と反しており
デザインドリブンイノベーションと同義。深く知るにはデザインドリブンイノベーションを知る必要はある。
仕事に活かすとしたら今扱っている商品の価値を深く考えて気づけるかということでしょうか。
tami_cks
その他
古きを温めて 新しきを知る
130mt_626
メーカー技術・研究・開発
ろうそくやモレスキンのように、形は変わらないが意味や解釈を変えることで、商品価値が見直される例は、なるほどと思った。マーケティング初心者のため、本講座から多くを学ぶことは難しかったが、また改めて振り返ってみたい。
asaiyo
専門職
自身の業務内容は問題解決型の思考が求められることが多い傾向にあるが、企業価値を向上させ、競合に買っていくためには新しい価値を見出す思考も必要。
課題に目を向けるだけでなく、自身の携わっている業務・事業の価値・意味を多角的な思考で考えていくことが、新しい価値を創出するためのカギとなる。
多角的な思考を習得するためには、日常において多くのことを観察し、どれだけの解釈があるか、深く考えていくことが必要となる。
mirai100
メーカー技術・研究・開発
意味のイノベーションでの手帳の話は興味深かった。ヨーロッパではロウソクが廃らないような事例を日本で探してみます。
marimo21
営業
電球とロウソクの話。時代と共に人が求めることの違いとイノベーションの話。
haok
IT・WEB・エンジニア
商品自体をアピールするのではなく、商品の使った新しいライフスタイルや価値観を提供することが意味のイノベーションなのかなと思いました。
個人的には『ひとりで考える』=コミュニケーションが苦手とか、協調性がないとかネガティブに考えがちでしたが、
ひとりで熟考することも大切だと肯定していいんだなと思えたことがよかったです!
kenji1217
販売・サービス・事務
一人で考えて見る。シンプルで説得力があります。
takayuki-maeda
営業
為になりました
kota_1218
営業
参考になった
ononta634
営業
後半はよかったです。
kobayashitakumi
専門職
あ
yasu197210
営業
グループ討議、ブレーンストーミングが主流な意見の出し方だと感じていたが、「1人で考える」ことの重要性を再認識できた。
面白い考え方だと感じました。
ロウソクがなぜ売れるのか。視点が広がります。
y-yoshi-
資材・購買・物流
一人で考える、さらには発信する重要性よくわかります。日本得意の周りに合わせる雰囲気もそれはそれでいいけど、イノベーションはそれだと何も起こらないなと。
takeshiketa
販売・サービス・事務
significanceなのかmeaningなのか。
kaeri
マーケティング
会社の商品において、質が悪いとか全てを決めつけるのではなく、そこから新たな価値を探してくる。
あるいは、商品に外にある価値をくっつけて、価値あるものにする、という発想を持つようにしたいと思う。
suke_suke
マーケティング
0→1だけがイノベーションではない
tommy3
マーケティング
イノベーション。アメリカのゼロイチ、欧州の既存価値組み合わせ。改めて理解を深めることが出来ました。
960004
クリエイティブ
今までは生活すべてを旧ソ連に決められていた国(エストニア・ラトビア・リトアニア)の人々が「これからは自分たちで全部決める」と過去と決別し、今の世界有数のデジタル都市が誕生した。会社が全て決めて、ただただそれに従っているだけの自分の姿が重なった。「意味のイノベーション」の考察をするまでにはいかなかった。しかし、性格的問題と劣等感強い小生には安西先生がおっしゃられていた「人に伝えないと何も始まらない、例えば好きか嫌いかをまず言う」というヒントはとても大きなアドバイスでした。ありがとうございました。
→「使い方はすべてあなた次第」 会社も手帳も・・・
モレスキンの手帳はかっこいいいけど、①値段が高い②きっちり1月から始まる(12月とかからでない)③日本の休日表記にならない ので使ったことがない。しかし2021、コロナ禍×アマゾン時代の販売戦略はどうしてるのか気になった。 最近は長細いトラベラーズノートの方が「自分で創っていく」という同様の文脈の中で売れているのではないかと思った(中目黒の店舗に世界中からトラベラーズノートファンが集まっている)。
欧州に詳しい安西先生の話は、
12月NHKで放送していたフランスの哲学者ピエールブルドューの「ディスタンクシオン」の社会的判断力批判を見ていたので何となくだが理解できた。
tsumo41630
IT・WEB・エンジニア
理解しました
ymatsum
販売・サービス・事務
自分の仕事では活用シーンがありませんが、普段の生活のなかでも意識してみれば新たな意味のあることに繋がる気がしました。
yuuki_ishi
営業
私も部下も含め、まずは「自分が考える」という工程を疎かにしてはいけない。あらゆるものに自分なりの解釈を加えることは常に意識してメモしていこうと思います。
今自分が携わっているビジネスはどこも同じようなサービスを提供しているので、まさにテクノロジーのイノベーションより意味のイノベーションの方が実現に燃えるものだと感じました。
takaraenamel
その他
意味のイノベーション→商品の意味を考える。価値を提供すること
が大切だと理解いたしました。
過去にあるものを新しく活用するというのは、新しく商品を開発する際に
必要な事だと理解出来ました。
一人で考える→ダメなことと思っていました。
何が美しくて、何が美しくないか?この機会に再度考えてみたいと思います。
minocchiyo
メーカー技術・研究・開発
意味のイノベーションはデバイス業界においても含蓄のある概念だと思いました。製品の特徴をあらわす仕様は複数あって、重み付けを変えることという意味なのかな、と。例えば、これまで処理速度ばかり注目されていたデバイスの魅力の切り口をかえて、処理速度はそこそこでも、低消費電力に特徴があれば、価値が見直されるみたいな動きがあってもいいかな、と。
意味のイノベーション=デザインドリブン、、、とされていたけれど、ここで言うデザインの定義を掴みきれませんでした。実設計ではなく、製品のコンセプト設計という意味でのデザインなのかな。
nakata_ke
IT・WEB・エンジニア
意匠としてのデザインでは無く、目的を達成する手法の設計としてのデザインについて一定の事前知識が無いと理解の難しいお話しと感じました。
スパーリングの行程の重要性を理解しつつ、先生が指摘されたよう日本の社会はこれがなじまない点も痛感します。批判は陰で行い、相手をくじくもので合って止揚としてより良いものを生む建設的なものではないと感じます。リトアニアはまだ問題意識がある点で良いかもしれません。日本はここに問題意識がまだ無いのかもしれません。
nakanishi-1261
営業
埋もれた価値を見出す事が大切と学んだ。
celt
クリエイティブ
「価値の創造」は製品やサービスなどを何か新たに作り上げることだけでなく、既にあるものの意味を変えたり、その忘れられていた価値に目を向けるというイノベートの方向もあるということに気付かせていただいた。呼び方を変えるだけでも新鮮味が出たりすることがあることは実生活でも感じて来た。
こういったことがうまくできれば、値下げ合戦やオマケをつける方向での付加価値アピールでの消耗戦を回避できると感じた。
kirish
専門職
イノベーションは、いつもと違うメンバーが出会うことで生まれるものだと思い込んでいましたが、
1人で考えてもイノベーションは起こるというのは驚きをもってお話を伺いました。また、だれでも出来ることなのだと、勇気づけられた気がします。
hirota901
マーケティング
意味のイノベーションは、特殊なテクロノジーがなくても、ものに価値を付与することができるので、私自身でも今ある製品について、何か気付けていない価値がないか考えてみたいです。また、日本では、1人で考えることがいけないことのような雰囲気があるというのは、確かにそういう部分があるなと思いました。
133
販売・サービス・事務
イノベーションの奥の深さを感じることができました。明日からの業務に役立てる
itoukitouk01
資材・購買・物流
意味のイノベーションは、テクノロジーに依存しなく、開発費用にそれほど費用がいらないため、何らかのイノベーションが起こせるということを理解した。
go_reds
営業
我々日本人は意見を表明することが一部の人を除いて不得意ですが、それを克服するため、まずは好きか嫌いか、そしてそれは何故かを熟考していく必要あると感じました。
y_iwasaki
その他
ゼロか1かの発想ではないイノベーション、過去の歴史の中なから新しい意味合いを見出すこともイノベーションの一つであると言われているが、そればリノベーションなのではないか
nao-gin
メーカー技術・研究・開発
具体性が理解できませんでした。
th_098112
メーカー技術・研究・開発
難解な講義だった
イノベーションというのはゼロからイチを作り出すというものを腹だけではなく既存のものに新たな見方や価値を与えるという方法もあるという点が学べた件
mitsunobu
マーケティング
意味のイノベーション、まず自分自身で深く考え情報を整理し、他者と衝突や交換を繰り返していく。
デザインシンキングは市場から聴取、意味のイノベーションは自分から市場へ。
意味のイノベーションは、既存のモノやサービスに新しい解釈や意味を与えることで新しい価値を生み出すことであり、テクノロジーに依存せずローコストで幅広い可能性を生み出すことができる。
kuta_41
IT・WEB・エンジニア
業務でばりばりつかえそうである。