
クリティカル・シンキング2(問題解決編)
「問題解決力」は新入社員から経営者まで、ビジネス、プライベートを問わず日常的に必要なスキルです。 そもそも問題解決とは何かを、正しい問題解決のステップと、各ステップでの留意点を踏まえながら学んでいきます。 ビジネスで発生する問題に対して考えるべき点を抜け漏れなく押さえながら、自分の考えを組み立て、解決策を立案するためのスキルを身につけましょう。 ※2020年3月31日、動画内のビジュアルを一部リニューアルしました。 内容に変更はなく、理解度確認テストや修了には影響ございません。
会員限定

















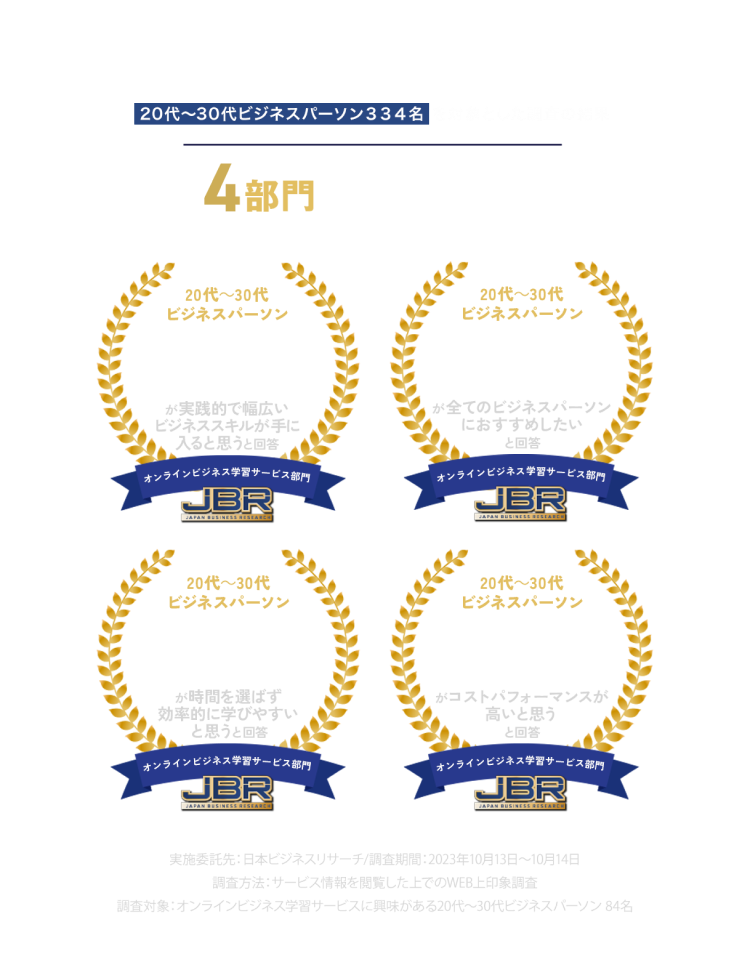

より理解を深め、他のユーザーとつながりましょう。
100+人の振り返り
hatomame_109026
経理・財務
私自身がボトルネックになっているのではと思うことが多くて、考えさせられる
hiro_yoshioka
メーカー技術・研究・開発
あらゆる戦略の基本。
発生したときの先まで読んで手を打っておくべし。
そして、自身がボトルネックになった場合は、臆せず他人に頼ることも重要だなと感じました。
普段からボトルネックを意識して、そこをカバーできる人材を目指す。
さらに、チャンスも逃さず、重要な局面での登場頻度を増やしたい。
目指させ リベロマスター ベッケンバウアー
makiko1729
メーカー技術・研究・開発
工場の生産ラインのように、何度も同じプロセスを繰り返すようなタイプの業務ではボトルネックの把握も比較的簡単なように思うが、複数人が同じ目的に向かって同時に作業を進めている際に、ある特定のメンバーの工程が進まないばっかりに全体が遅延する、というようなタイプのボトルネックもある。プロジェクト運営の立場から、随時そのようなボトルネックが起こっているかいないかを確認しながら、ボトルネックが起こっている際にはリソース投入などの措置を取りながら進めることが大事と思う。
kkats
その他
多能工化と専門性強化のトレードオフには注意が必要だ
harunosuke
その他
昔読んだ「ザ・ゴール」でもボトルネックがキーでしたね。実際に、クリティカルな作業工程だと、どこかにボトルネックは発生しますよね。そこを見定めるのがポイントですね。
tokutoku230
メーカー技術・研究・開発
実験のPDCAを人数かけてボトルネック解消に努めていますが、人(who)以外、 what,when,where 含めてトータルで考え解消することが大事だと思いました。特に、社外にどれだけ協力頂けるかによっても変わると思います。
kim1007
経営・経営企画
多能効果がボトルネックを解消するという観点はなかった。早速取り掛かってみたい。
ttkkkat
営業
複雑な仕組みのものでも業務が円滑に進まない場合はどこにボトルネックがあるのか原因を確認することは必要だと思う。
terasawa
その他
工程において重要な考え方です。複雑な工程においてもきちんと分析することが必要と改めて感じました。
saito-yoshitaka
メーカー技術・研究・開発
ボトルネックの原因系を把握する事で効率的な打ち手を打つことが重要、
ishii201
営業
ボトルネックは定性的な価値尺度が入らないよう、科学的な定量分析に置き換えられることが鍵
huez
IT・WEB・エンジニア
日頃の業務プロセスの改善に活用できると思われます。
yoccha
メーカー技術・研究・開発
特に製造業の生産プロセスに携わる方に有用と思います。
sumomo_koume
IT・WEB・エンジニア
日々の業務の中で活用していきたい。
maja
営業
生産工程だけでなく、日常の生産性の観点からも、業務を定量化し、どこがネックになっているのか、時間がかかっているのかの把握と解消を行う必要があると感じた。
araki_yoshinobu
クリエイティブ
非定型作業なので、学習した視点で業務全体を無渡すことが大切
yoshihoriuchi
経営・経営企画
自社にいかに当てはめて考えるか、具多例をたくさん見たい❗️
sanamama8119
資材・購買・物流
生産性を上げるために全ての工程を均等に増設するのでは無駄な費用が掛かる上、効果が現れにくいことを学びました。
megu-a
その他
ボトルネックの意味と調整により生産性を上げる関係性がよく分かりました。
自分の業務について全体量を把握し、ボトルネックを発見することをまず心がけたいと思います。
daxanan
営業
ボトルネック
atsu_76
メーカー技術・研究・開発
ボトルネックの解消法を学んだ
hr-sakai
その他
ボトルネックを見つけて対処しないと改善しないし、効率化もはかれない。
nishidate_t
IT・WEB・エンジニア
ボトルネックを解消することで、全体の生産性は向上しますが、品質的な部分で見落としが発生する可能性を秘めていることも考えられます。
bm90007
営業
ボトルネックがどこかを常に意識したい
masa12361
メーカー技術・研究・開発
ボトルネックになっている部分を明確にして、補強することで生産性を上げる事ができる。
h_dice-k
メーカー技術・研究・開発
ボトルネック
kei3222
販売・サービス・事務
振り返ると基本的にどのような業務においてもフローの整理・生産キャパシティの考え方は適用できると気が付いた。
業務改善の際にはボトルネックを改善する意識を常に持つようにする。
tm03
メーカー技術・研究・開発
オペレーション改善は思いつくが、多能工化はなるほどと思いました。的確に原因を捉えることが重要。
tozaki3104
専門職
ボトルネックを正しく把握し、改善することの重要性がよく分かりました。
tadashi-0413
その他
ボトルネックの考えが非常に理解出来た。現場で実践可能。
stoneriver1118
マーケティング
生産性が低い部分と見極め、人員配置などの対策をとることが重要だと思いました
kosei_takagi
その他
先ずはプロセスの洗い出しとキャパシティの把握が絶対だ。。。
tokyolifeline
営業
.............................................
robber_2019
営業
Bottlenecks are important to increase productivity.
john-taro
マーケティング
人材配置をボトルネックという視点で考えたことがなかったため、勉強になった
myuu
専門職
多能工化と専門性強化のトレードオフというのが印象的でした。広く浅くが得意な人、一つのことを深堀するスペシャリスト、組織の様々な人員を適材適所に配置することが大切だと改めて感じました。
hamada--
その他
以前いた部署は同じ専門性を持った人員が私以外いない時期がありました。繁忙期は他の職層の方に手伝ってもらいましたが、これもボトルネックの一例だなと思いました。
tashirooo
営業
改めて勉強になりました
yuuba
メディカル 関連職
非体型業務だからと言ってボトルネックを探さなくて良いわけではない。を実践的に考えると、何か新たな施策をはじめるにあたって時間がかかりがちな「情報収集」の区切りを意識することが大事かなと思いました。イメージとして、準備度0を60にするのと、80を90にするのとで同じくらい時間がかかるとしたら後者をやりすぎないようにするとか。、
tom-_-
専門職
現在の業務にそのまま適用するのは難しそうだが、分析的に業務を把握し、適用について考えていきたいと思う。
hiro-math
メーカー技術・研究・開発
ボトルネックはどこに発生しているかを考えて生産性向上にむけて活動していきたいと思います
mnakao1984
経営・経営企画
業務で歩行をするためには、観察は非常に重要となる。
px_0001
メーカー技術・研究・開発
生産スピードを制限する工程を見抜き,柔軟な資源活用や増強を行うことが重要.
sharpspoon
資材・購買・物流
日常業務の中の生産性向上検証
tktk_yk
営業
既に理解している内容であった。
satotaka_com
IT・WEB・エンジニア
ボトルネックになっているパートに対する人的リソースの再配置、経営資源の再配分
nabeuchi
メーカー技術・研究・開発
ボトルネックを掴み現場の改善をすすめていきます
yyyuina
販売・サービス・事務
日々ルーティン業務がほとんどですが、効率化できる箇所はないか考えをやめないようにしたいです。
omokun
経営・経営企画
手待ち時間が出来ていれば、
業務にかたよりがありボトルネックになっている可能性がる。
ボトルネック箇所と原因の分析が大事
masa_0125
IT・WEB・エンジニア
業務分析に重要な指標。
日々の業務でも取り入れてみる。
kimkota
営業
ボトルネックを簡単にいうと、業務プロセスにおいて足を引っ張っている部分と言い換えることができるかもしれない。複数人が関わる業務プロセスだけでなく、個人業務においても日々の業務を棚卸しすることで、どこにムダが生じているのか、あるいはスキル不足のため時間がかかっているのかを把握することで業務効率の改善につながると思いました。
ynomurauk001
人事・労務・法務
非定型業務といっても、創造的な部分は全体のうちごく僅かな部分に過ぎないケースが多く、きちんと工程バラシを行うと定型業務の複合集約に結局落ち着くので、音を上げずに工程の究明を行うとうまくゆくケースが殆どですよね。
nishimura4900
IT・WEB・エンジニア
このような機会を与えていただき感謝してます。
leo1214
その他
概念は理解しているので、それを以下に解消するかが重要だと思いました。
ryoji49841
資材・購買・物流
日常業務における事務処理についても電算処理等のタイミング、スピードでボトルネックが発生している部分があるのでその解消に向けて定量的な実績値をもとに改善を図っていくことに活用可能。
sakiyam2
IT・WEB・エンジニア
要員のスキル不足に起因するボトルネック発生に頭を悩ませることが多い。要員の配置換えで対応することが多いが、結局高いスキルを持つ要員の負担が増えただけになることが大半で、目指すべき改善にまでは至らない。現実的な解決策は今のところ見つかっていない。
tkd_t
人事・労務・法務
非常に分かりやすく、役立ちました
ikep_gp
IT・WEB・エンジニア
多能工化は万能ではない。専門性強化が犠牲になりかねないのでバランスを図ることが大事。
shiver
メーカー技術・研究・開発
違う場面で聞いたことがあったが、業務において実際に考えたのは初めてだった。今後は業務中にもより意識していきたい。
sobayashi62
メーカー技術・研究・開発
作業効率の改善に生かせると思います。
arakawa_88gou
営業
ボトルネックについて理解が深まった
stake_pana
経営・経営企画
特に効率に関する課題が発生した時の対策検討の考え方の柱になる。
soshin_1226
建設・土木 関連職
とても、当たり前の事でした。
f-233
販売・サービス・事務
ボトルネックとは1つの要因で全体の結果を左右する、最大の要因。解消することで、最も全体の成果を向上させることになる箇所。
複雑な業務にも潜んでおり、分析及び特定をあきらめないことが大切。
またその箇所がボトルネックである背景や原因も掴むことがより良い。
nu_midori
経営・経営企画
業務改善において自社でも有効な考えなので、さっそく取り入れたい。
kosei_s
営業
1つの課題においてもよく考える必要がある
gakut
メーカー技術・研究・開発
非定型業務でも改善点を洗い出すのにボトルネックを考えるのは有効であると学んだ
miyabi141
その他
昔、本で読んだ様な・・・
lado
販売・サービス・事務
やみくもに人を増やせばよいものではないのはことを理解できた
shirota_do
資材・購買・物流
ボトルネックは、納期、生産性に関わる事ですから、
先ずは現場においては、
作業者の安全が確保され、
お客様に品質を担保できる商品を作る、
その2つがクリアできての改善ですから、
順番を間違えてはいけません。
生産能力を上げる方法は、
セル、ライン、専門工、多能工と
生産方式によっては
バランスが重要ですので、
生産する商品群によって、
合わせる必要があるのも、
仕事をする醍醐味です。
toshibon
営業
主に工場での流れ作業を思いながら考えてみるとよく理解できた。
また、朝の通勤時の混雑する駅の改札も一種のボトルネックになっている?のかもしれないと、いろんな場面に置き換えながら考えたりすると世の中にはたくさんあるなぁと思いました。
mamaruru
マーケティング
業務進捗が悪い場合や、過去の取り組みを参照する際に、全体だけではなく部分的に分析して原因をつきとめることが大切
iijima-miyako
営業
自分の業務で言うと、多能工可を高める事で少ない人材でもその人材以上のスピードで業務を行うことが出来ると思いました。
tp4
営業
日常メンバーが行っている業務でボトルネックの有無を意識していなかったので、改めて業務の工程を確認し、ボトルネックの有無、あった場合の改善に着手したい。
k12312
IT・WEB・エンジニア
業務経験を積む過程で、ネックも変化するように思う。(新人なら知識や社内人脈、中堅では自身の手数、…)
常に見直して改善の余地を検討することが必要に思う。
yutaka_aimar
営業
普段から自身がボトルネックになった場合を想定して臆せず他人に頼ることも大事だと感じました。いろんな日常の場面に置き換えることができると感じました。
maytokyo
マーケティング
ボトルネックについて、生産量のキャパシティーについてが軸にありましたが、
クイズでクオリティについてを問う問題があり、悩ましかったです。
クオリティ視点のボトルネックについても思考したいです
sample_account
マーケティング
非定形業務では分析が難しい。業務従事者が常に「何がボトルネックになっているか」とアンテナを立てる必要がある
tomon_2021
IT・WEB・エンジニア
否定形業務におけるボトルネックを考えると、知識や経験、要求に対する対応力、顧客の性格などによっても変化することが予想されます。
人の能力の定性、定量の基準をもって対応を検討する必要があると思いました。
yuribis
専門職
実務では多能工化と専門業務とのバランスを実現することが課題だと感じた
mori_yasunori
販売・サービス・事務
自身の業務においてどこがボトルネックとなっているかを正しくまず把握する、改善するにあたりどの部分を改善していくのかを明確にしていく必要がある。
seita_hirofumi
経理・財務
自身や組織の業務にボトルネックを考え多能工化や人材を育てることにより高い生産性を見出すことを考え出すことが肝要。
tai_n
メーカー技術・研究・開発
日々の業務で時間がかかっている工程に関して原因を分析し、適切な改善策を取ることに活用する。
non_xx
販売・サービス・事務
生産性向上のためには、ボトルネックの考え方を活用し、効果のある対策をとれるようにしていきたいです。
sa-t
営業
スピードの阻害になっている一番のつっかえを探すことが大切
takap79
人事・労務・法務
工場と違い事務職場でのボトルネックの発見と改善は難しく、生産性が低下している要因を詳らかに発掘する必要があるのでは、と感じた。
shimoosako
人事・労務・法務
しっかり悪いところを見極め、適切な改善を行います。
eiken-saito
その他
自らの業務においてボトルネックになっている業務を洗い出し改善したい。
io-daisaku
営業
わかりやすかったです。現場のスタッフには、きちんと見えるように、わかるように説明して、カイゼンを行う必要があると思います。
satopon1
その他
在籍している部署における業務のボトルネックを検討する上で、解消法としてどうしても多能工化(マルチスキル)が思い浮かぶ。ただそれ以前に深刻な課題は、人材が慢性的に不足していることと人が育っていないことだ。
yasuo-k
IT・WEB・エンジニア
ボトルネックを把握するところが大事
bondmura
経営・経営企画
ボトルネックが定量的に測れない場合、またはその数値が根拠かわからない場合がまた課題。 仮説を設定するしか無いかなぁ
momotako
メーカー技術・研究・開発
ボトルネックについて深く学ぶことができた
10shi-253
メーカー技術・研究・開発
既存設備に新しい商品を流す場合に、各工程時間を比較分析して各工程サイクルタイムがラインサイクルタイム以下になるように、ボトルネック工程を見つけて工程偏差に偏りが出ないように製品設定と工程設定を行う
saso_h
その他
業務においてボトルネックとなっている部分を考え、多能工化を活用して、誰でも担当できるようになると顧客・他部門からの問い合わせにも対応でき、信頼度があがると感じた。
hase26
営業
勉強になりました
nemo_h
建設・土木 関連職
生産者からして、全体の進行を調整する手段となる
altego_chf_sal
販売・サービス・事務
常に業務全体の流れを俯瞰する事を習慣付け、
ボトルネックの見極めを行っていく。
sakurai-ttt
メーカー技術・研究・開発
例で出てきたようなわかりやすいものばかりでないのが現実であるが、それでも分解・分析しボトルネックとなっている部分の解消が最大の効果を生むと考えられる。思い込みではなく客観的にも説明がつくよう分析して答えを出していきたい。
ace_2021
人事・労務・法務
仕事の進め方や人員の配置状況を踏まえ、ボトルネックとなっている工程(方法)を見極めたうえで、業務改善につなげていきたい。
業務が複雑に絡みあっていたり、個人の得意・不得意が関係している部分もあるため、どこに一番問題があるのかを見極めることは難しいものの、人を増やすことで重複業務が発生したり、手待ち時間が発生したりと効率的にならないことが多いため、複眼的に分析をしたうえで、対策を講じていきたい。